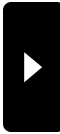2012年01月25日
シフトレンズのテスト
画像ソフトで画像の変形コマンドを使って建物の線を出してみたりしていたのですけど、シフトレンズを使って見ることにしました。
夜の撮影でしかも手持ちなんですけど、どんなものかと思いまして。
こちらは鹿児島市の市役所、伊敷支所。

やっぱり、スキッと線が出ている画像は落ち着いて見られるから好きです。
使用レンズは PC-Nikkor 28mm f2.8 というもの。
カメラはD700 ISO3200 1/30 F2.8
専門的に画像を撮る人たちのブログや掲示板を見ていると、こうしたアオリ撮影などが出来る特殊な機材というものは後五年も経てばゴミになるという話で、通常の撮影を行った後デジタル処理でやる方法を覚えた方がいいということなんですけどね。どうなんでしょう。コダックの破産申請とか、世の中の変化がダイナミックすぎてただビックリします。
こちらは鹿児島市の伊敷台にある住宅。

同じ撮影位置から別なカメラで撮ったもの。
D300でDX 18-55 3.5-5.6 VR 18mmで撮影。ISO6400 1/80 F3.5

夜の撮影でしかも手持ちなんですけど、どんなものかと思いまして。
こちらは鹿児島市の市役所、伊敷支所。

やっぱり、スキッと線が出ている画像は落ち着いて見られるから好きです。
使用レンズは PC-Nikkor 28mm f2.8 というもの。
カメラはD700 ISO3200 1/30 F2.8
専門的に画像を撮る人たちのブログや掲示板を見ていると、こうしたアオリ撮影などが出来る特殊な機材というものは後五年も経てばゴミになるという話で、通常の撮影を行った後デジタル処理でやる方法を覚えた方がいいということなんですけどね。どうなんでしょう。コダックの破産申請とか、世の中の変化がダイナミックすぎてただビックリします。
こちらは鹿児島市の伊敷台にある住宅。

同じ撮影位置から別なカメラで撮ったもの。
D300でDX 18-55 3.5-5.6 VR 18mmで撮影。ISO6400 1/80 F3.5

2012年01月19日
最近読んだ本:みんなの写真・ソーシャル時代の写真の撮り方
最近読んだ本の中で写真関連のもののうち、読んで良かったなぁと思ったのはこれです。
楽しい みんなの写真 ソーシャル時代の写真の撮り方・楽しみ方
アマゾンのページだと
http://www.amazon.co.jp/%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%84%E3%81%BF%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%AE%E5%86%99%E7%9C%9F-%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%8B%E3%81%8F%E6%92%AE%E3%82%8B%E3%80%81flickr%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%82%8B%E3%80%82%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AE%E6%92%AE%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%BF%E6%96%B9-%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%AB%E3%81%BE%E3%81%95%E3%81%8D/dp/4861007542
です。
http://blog.zikokeihatu.com/archives/-flickr.html
携帯電話が爆発的に普及し、それに付くようになったiモードなるものがネットの一大勢力になってさらには電話にカメラ機能がつくようになって写メールなんてものが出てきたあたりから素人が素人なりに楽しむ「写真」って、無視できない存在なのではないかと、10年くらい前に考えたことがあります。
私はずっと以前からカメラや写真が好きでしたけど、携帯が出てきて以降の写真の意味ってのが気になっていました。
その辺のことがこの本に出ています。
もちろん、新しい写真ってのはデジタルのテクノロジーを下敷きにしているものです。
その写真ってのは、銀塩って呼ばれる昔からの写真とはまったく様子の違うテクノロジーで実現されているわけです。
写真行為そのものは銀塩でもデジタルでも変わらないと思うのですけど、楽しみ方、楽しまれ方は随分と違っていると思います。
銀塩ジジィってのが「デジタルなんかニセモノでしかない」っていう気分もわかる自分ですけど、一方で新しい写真がワクワクするものでもあるのは、事実ですし、紛れもなく現実ですし、否定するのは現実を否定することでもあるから、そんなことをするのは後ろ向きだと思うわけです。
そう思う自分が写真を撮るのは、どうしてだろうと思ったときに、わからなくなるわけです。
このことでネット上で議論してかなり消耗してしまったこともあります。
その時の経験についての答えを出したいという気持ちもあったんですけど、この本が見事にそれを説明し、実践してしまっているのでかなりすっきりしたと、そういうことなんです。
まえがきには、「写真がうまくなりたいかと言われたらうまくなりたいと思うけど、じゃ、何のためにうまくなりたいのか?」って問いが書かれています。
もしかしてうまい写真が撮りたいのではなくて、「うまい写真が取れる証拠写真が撮りたいだけなんじゃないか」って畳みかけてくるわけです。
なるほど、そうだ。
自分だってこの位なら撮れるぜ、という見本を(証拠を)撮りたいんだ。
でも、そんなことをする必要のない時代になっているのだ、ということなんです。
まぁ、詳しいことは本に書いてあります。
で、Flickrです。
もう5年以上も前にアカウントを取って放置していたんですけど、改めてじっくりつきあってみようと思い、プロアカウントにして再スタートしました。
http://www.flickr.com/people/13401501@N08/
これで見れるかしら?
ネットのサービスで2004年にスタートしたものがずっと続いているというのは、かなり長持ちの方じゃないかと思われます。この先何年続くのかわからないけど、とりあえずFlickrは私も続けてみようと思います。
facebookとかtwitterはいまいちなじんでないんですけどね。mixiはソーシャルネットワーク独特の窮屈さがあって、あまり乗り気でやってはいないんです。
Flickrも言われて気がついたけど、実は巨大なソーシャルネットワークなんです。だけど、あまり濃密な付き合いじゃないというところがいいです。

鹿児島市紫原 鹿大通りに接続する新しい道を作っている所。歩行者用の? 階段のようですが、手すりがまだ付いていなので、ここを歩くとかなり怖いのかも。

鹿児島市宇宿町にて。曇天でモノクロっぽい光景。
楽しい みんなの写真 ソーシャル時代の写真の撮り方・楽しみ方
アマゾンのページだと
http://www.amazon.co.jp/%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%84%E3%81%BF%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%AE%E5%86%99%E7%9C%9F-%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%8B%E3%81%8F%E6%92%AE%E3%82%8B%E3%80%81flickr%E3%81%A7%E8%A6%8B%E3%82%8B%E3%80%82%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AE%E6%92%AE%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%BF%E6%96%B9-%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%AB%E3%81%BE%E3%81%95%E3%81%8D/dp/4861007542
です。
http://blog.zikokeihatu.com/archives/-flickr.html
携帯電話が爆発的に普及し、それに付くようになったiモードなるものがネットの一大勢力になってさらには電話にカメラ機能がつくようになって写メールなんてものが出てきたあたりから素人が素人なりに楽しむ「写真」って、無視できない存在なのではないかと、10年くらい前に考えたことがあります。
私はずっと以前からカメラや写真が好きでしたけど、携帯が出てきて以降の写真の意味ってのが気になっていました。
その辺のことがこの本に出ています。
もちろん、新しい写真ってのはデジタルのテクノロジーを下敷きにしているものです。
その写真ってのは、銀塩って呼ばれる昔からの写真とはまったく様子の違うテクノロジーで実現されているわけです。
写真行為そのものは銀塩でもデジタルでも変わらないと思うのですけど、楽しみ方、楽しまれ方は随分と違っていると思います。
銀塩ジジィってのが「デジタルなんかニセモノでしかない」っていう気分もわかる自分ですけど、一方で新しい写真がワクワクするものでもあるのは、事実ですし、紛れもなく現実ですし、否定するのは現実を否定することでもあるから、そんなことをするのは後ろ向きだと思うわけです。
そう思う自分が写真を撮るのは、どうしてだろうと思ったときに、わからなくなるわけです。
このことでネット上で議論してかなり消耗してしまったこともあります。
その時の経験についての答えを出したいという気持ちもあったんですけど、この本が見事にそれを説明し、実践してしまっているのでかなりすっきりしたと、そういうことなんです。
まえがきには、「写真がうまくなりたいかと言われたらうまくなりたいと思うけど、じゃ、何のためにうまくなりたいのか?」って問いが書かれています。
もしかしてうまい写真が撮りたいのではなくて、「うまい写真が取れる証拠写真が撮りたいだけなんじゃないか」って畳みかけてくるわけです。
なるほど、そうだ。
自分だってこの位なら撮れるぜ、という見本を(証拠を)撮りたいんだ。
でも、そんなことをする必要のない時代になっているのだ、ということなんです。
まぁ、詳しいことは本に書いてあります。
で、Flickrです。
もう5年以上も前にアカウントを取って放置していたんですけど、改めてじっくりつきあってみようと思い、プロアカウントにして再スタートしました。
http://www.flickr.com/people/13401501@N08/
これで見れるかしら?
ネットのサービスで2004年にスタートしたものがずっと続いているというのは、かなり長持ちの方じゃないかと思われます。この先何年続くのかわからないけど、とりあえずFlickrは私も続けてみようと思います。
facebookとかtwitterはいまいちなじんでないんですけどね。mixiはソーシャルネットワーク独特の窮屈さがあって、あまり乗り気でやってはいないんです。
Flickrも言われて気がついたけど、実は巨大なソーシャルネットワークなんです。だけど、あまり濃密な付き合いじゃないというところがいいです。

鹿児島市紫原 鹿大通りに接続する新しい道を作っている所。歩行者用の? 階段のようですが、手すりがまだ付いていなので、ここを歩くとかなり怖いのかも。

鹿児島市宇宿町にて。曇天でモノクロっぽい光景。
2012年01月15日
頴娃町の大根干し
先日用事があって頴娃町に行きました。
このあたりは毎年冬になると、大根干しの風景が見れます。

お昼を食べにトラックに乗って移動中に見かけた風景をパチリ。
この日は風のない日でそんなに寒くなかったけどどんより曇天。陽が差してたらカラーでバッチリ写せば絵になったかも。わざわざ車を止めてーとは言い出せず、眺めて終わりでした。

車のガラスを通すとコントラストが下がるんですね。
Nikon D700 + Ai マイクロnikkor 55mm f2.8 ISO720 1/800 F11
このあたりは毎年冬になると、大根干しの風景が見れます。

お昼を食べにトラックに乗って移動中に見かけた風景をパチリ。
この日は風のない日でそんなに寒くなかったけどどんより曇天。陽が差してたらカラーでバッチリ写せば絵になったかも。わざわざ車を止めてーとは言い出せず、眺めて終わりでした。

車のガラスを通すとコントラストが下がるんですね。
Nikon D700 + Ai マイクロnikkor 55mm f2.8 ISO720 1/800 F11
2012年01月15日
ニコン 50mm f2 古いもの同士の比較(古い方が好み)
シャッター切って、シャープな画像が撮れていたときの快感が写真の楽しみなんですが、デジタルになってからそれであたりまえになりすぎちゃったのかなぁと思うときがあります。昔は、「現像したらピンぼけで失敗だった」なんてセリフはあたりまえに聞いてました。今はあまり聞かなくなった気がします。写っててあたりまえなんですよね。
画面全体にピントが来ているシャープでパンフォーカスな画像もいいけど、ぼけた部分が味を出している画像というのも撮ってみたいです。そうした写り具合を決定するのがレンズです。それを撮りたかったら、そういう写りをするレンズを手に入れる必要があるわけです。
では、ぼけている部分が映り込むレンズならどれでもいいかというと、ボケ味がいいレンズ、そうでないものという言い方が昔からあります。自分が愛用しているニコンというメーカーは、そのボケ味も写り具合も「硬い表現」だという評価が定着しています。シャープにきっちり写すにはニコンのレンズは高性能だけど、写真表現はそれ一辺倒ではないのが難しくもあるところ。
それゆえ、ニコン以外のメーカーが、各社特色を持って製品を出していて、それぞれにファンがいるという感じでしょうか。そのニコンに取り付けられるニコン製以外のレンズも存在しています。そんな中から「ニコンらしくない描写」をするレンズを手に入れたら、また別の楽しみが増えるということにもなるわけです。
写真を趣味にする人は多くて、写真関係のブログをあちこち見ていると同じようなことを誰もが考えていたりするわけで、口径の大きな単焦点レンズで派手に背景をぼかした画像が流行っている感じもします。ぼけていればぼけているほど良かったり面白かったりなので、そうした画像は沢山見つけられます。
私もやってみたいと思っていても、買い物にはお金がかかりますので、あまり思うに任せないという事情もあるわけです。
そんな中 Flickr でこの画像を見ました。
http://www.flickr.com/photos/f_blue/3861260857/in/faves-13401501@N08/
意外なところに意外なものが存在していたんだなという感じ。
背景がドロドロにぼけているのではなく、存在感を持って主題と関係を保っているというかなんというか、そういう感じの画像も雰囲気良さそうです。
Flickrの画像が撮影されたレンズは昔のレンズ。ニコンのFマウントなので、今のデジタル一眼にも使えます。昔の標準レンズなので、沢山流通していて中古で容易に入手できます。
画像のレンズはその50mm標準レンズのなかでもf1.2やf1.4という高級品? ではなくf2という「普及型モデル」なんです。その普及型もf1.8が発売されて生産中止になってしまい、影が薄くなっているような存在のレンズです。
そんなレンズがとてもいい描写をするらしいのです。中古でも程度が余りよくないものは安価に入手できるようなので、早速買って試してみたというわけなのです。
その後ネットで、「モデルチェンジされて新しくなるものが必ずしも良い方向に変化するとは限らない例」として語られているのも見ました。
そうしたこともあって、flickrでは Nikkor-H C 50mm f2 と、モデル名が明記してあります。50mm f2 であっても、この代のモデルがいい空気感を持っているというわけです。

Nikkor-H C と、その後の Nikkor としか刻まれていない後のモデルの二つを入手して比べてみた画像です。上の画像に二つレンズが写っているうちの右側のものがH C。
ニコンは以前から使っているんだけど、あまりマニアックな興味がなかったものだから、今回初めてニコンのFシステムの変遷などを知ったしだいです。HCはムカーシの、いかにもニコンという感じのデザインです。
このレンズは点光源をはっきり写し込むと、ボケ玉の縁が濃い線でふちどりされるとか、絵柄によっては二線ボケでうるさくなるという話は事前にネットで聞いています。
今回は玉ボケが出るようなシーンではない普通の光景を試し撮りしたものです。

何の面白みもないシーンです。でも、こんな感じの画像は沢山撮るだろうと思われます。もちろん、真ん中に主題の人物やらなんやらはいってくるわけですけど。背景だけ抜いてきたようなものという感じの画像だと思えば、特殊なもんじゃないですよね。国道のひび割れ部分にピントを合せてあります。センターラインやガードレールなどは後ピンの中です。さらにその後ろの植物がガサガサしているところを等倍で切り抜いた画像がこれです。
↓Nikkor 50mm f2 f2.8で撮影 ボディーはD700

Nikkor H C 50mm f2 f2.8で撮影、ボディーはD700

HCの方を使っていて、比較してみようと思いついて入れ換えたのですが、その場でカメラのバック液晶で画像を確認しているだけでも、新しいNikkorの方がシャープでくっきりしていて、国道を通るトラックのメッキのバンパーなど、メタリックなものの表現がはっきり写り、気持ちいい感じです。同じ傾向の写りながらも、シャープ感がぐっと向上している感じなのです。その場ではこちらの方がいいじゃんと思ったのです。
後で家に帰ってから上のような比較をしてみると、植物の葉っぱの照りがしっかりボケ玉になっていて、例の縁取りが出ているんですね。ボケ玉というのはいつでも出来るのかと思った次第。そしてNikkorの方は植物の蔓などがはっきり二線ボケになっていて、ごちゃごちゃ感の増幅が。
シャープな写りと引き換えに、二線ボケがやってきているようです。
目に見えるシャープ感がないものの、HCのふんわりした線の細い描写はやはり「ニコンらしくない柔らかな描写」だというのは納得できたという次第です。
次のブログエントリーに、Ai Nikkor 55mm f2.8 マイクロレンズで撮影した大根の画像を貼る予定です。画像を用意しながら「硬いなぁ」と思いました。HCとそうでないもの二本の50mm よりはるかに硬い画像です。それを見れば、どちらの50mm f2は柔らかいんですね。
HCの50mm f2をどんどん使ってみようと思った次第です。
画面全体にピントが来ているシャープでパンフォーカスな画像もいいけど、ぼけた部分が味を出している画像というのも撮ってみたいです。そうした写り具合を決定するのがレンズです。それを撮りたかったら、そういう写りをするレンズを手に入れる必要があるわけです。
では、ぼけている部分が映り込むレンズならどれでもいいかというと、ボケ味がいいレンズ、そうでないものという言い方が昔からあります。自分が愛用しているニコンというメーカーは、そのボケ味も写り具合も「硬い表現」だという評価が定着しています。シャープにきっちり写すにはニコンのレンズは高性能だけど、写真表現はそれ一辺倒ではないのが難しくもあるところ。
それゆえ、ニコン以外のメーカーが、各社特色を持って製品を出していて、それぞれにファンがいるという感じでしょうか。そのニコンに取り付けられるニコン製以外のレンズも存在しています。そんな中から「ニコンらしくない描写」をするレンズを手に入れたら、また別の楽しみが増えるということにもなるわけです。
写真を趣味にする人は多くて、写真関係のブログをあちこち見ていると同じようなことを誰もが考えていたりするわけで、口径の大きな単焦点レンズで派手に背景をぼかした画像が流行っている感じもします。ぼけていればぼけているほど良かったり面白かったりなので、そうした画像は沢山見つけられます。
私もやってみたいと思っていても、買い物にはお金がかかりますので、あまり思うに任せないという事情もあるわけです。
そんな中 Flickr でこの画像を見ました。
http://www.flickr.com/photos/f_blue/3861260857/in/faves-13401501@N08/
意外なところに意外なものが存在していたんだなという感じ。
背景がドロドロにぼけているのではなく、存在感を持って主題と関係を保っているというかなんというか、そういう感じの画像も雰囲気良さそうです。
Flickrの画像が撮影されたレンズは昔のレンズ。ニコンのFマウントなので、今のデジタル一眼にも使えます。昔の標準レンズなので、沢山流通していて中古で容易に入手できます。
画像のレンズはその50mm標準レンズのなかでもf1.2やf1.4という高級品? ではなくf2という「普及型モデル」なんです。その普及型もf1.8が発売されて生産中止になってしまい、影が薄くなっているような存在のレンズです。
そんなレンズがとてもいい描写をするらしいのです。中古でも程度が余りよくないものは安価に入手できるようなので、早速買って試してみたというわけなのです。
その後ネットで、「モデルチェンジされて新しくなるものが必ずしも良い方向に変化するとは限らない例」として語られているのも見ました。
そうしたこともあって、flickrでは Nikkor-H C 50mm f2 と、モデル名が明記してあります。50mm f2 であっても、この代のモデルがいい空気感を持っているというわけです。

Nikkor-H C と、その後の Nikkor としか刻まれていない後のモデルの二つを入手して比べてみた画像です。上の画像に二つレンズが写っているうちの右側のものがH C。
ニコンは以前から使っているんだけど、あまりマニアックな興味がなかったものだから、今回初めてニコンのFシステムの変遷などを知ったしだいです。HCはムカーシの、いかにもニコンという感じのデザインです。
このレンズは点光源をはっきり写し込むと、ボケ玉の縁が濃い線でふちどりされるとか、絵柄によっては二線ボケでうるさくなるという話は事前にネットで聞いています。
今回は玉ボケが出るようなシーンではない普通の光景を試し撮りしたものです。

何の面白みもないシーンです。でも、こんな感じの画像は沢山撮るだろうと思われます。もちろん、真ん中に主題の人物やらなんやらはいってくるわけですけど。背景だけ抜いてきたようなものという感じの画像だと思えば、特殊なもんじゃないですよね。国道のひび割れ部分にピントを合せてあります。センターラインやガードレールなどは後ピンの中です。さらにその後ろの植物がガサガサしているところを等倍で切り抜いた画像がこれです。
↓Nikkor 50mm f2 f2.8で撮影 ボディーはD700

Nikkor H C 50mm f2 f2.8で撮影、ボディーはD700

HCの方を使っていて、比較してみようと思いついて入れ換えたのですが、その場でカメラのバック液晶で画像を確認しているだけでも、新しいNikkorの方がシャープでくっきりしていて、国道を通るトラックのメッキのバンパーなど、メタリックなものの表現がはっきり写り、気持ちいい感じです。同じ傾向の写りながらも、シャープ感がぐっと向上している感じなのです。その場ではこちらの方がいいじゃんと思ったのです。
後で家に帰ってから上のような比較をしてみると、植物の葉っぱの照りがしっかりボケ玉になっていて、例の縁取りが出ているんですね。ボケ玉というのはいつでも出来るのかと思った次第。そしてNikkorの方は植物の蔓などがはっきり二線ボケになっていて、ごちゃごちゃ感の増幅が。
シャープな写りと引き換えに、二線ボケがやってきているようです。
目に見えるシャープ感がないものの、HCのふんわりした線の細い描写はやはり「ニコンらしくない柔らかな描写」だというのは納得できたという次第です。
次のブログエントリーに、Ai Nikkor 55mm f2.8 マイクロレンズで撮影した大根の画像を貼る予定です。画像を用意しながら「硬いなぁ」と思いました。HCとそうでないもの二本の50mm よりはるかに硬い画像です。それを見れば、どちらの50mm f2は柔らかいんですね。
HCの50mm f2をどんどん使ってみようと思った次第です。
2012年01月12日
レンズの目(ボケ表現とボケ玉、f1.4)
MFレンズを何本か増やしました。
現代風にくっきり写るものも欲しいけど、ふんわりしっかり写るものも欲しかったんです。
それにしても、50年基本構造が変わらないというニコンのFマウントはすごいなと思います。
昔のレンズが今でも使えるからです。
マウント口径を大きく作ってあるキヤノンの一眼レフカメラにマウントアダプタを付けてニコンを始めさまざまなレンズが付けられるようで、これはこれで面白そうです。ペンタックスやミノルタの銘玉が使えるみたいだし、スクリューのライカなども付けているみたいです。
このあたりの楽しみというのは、その先リコーのGRなどレンジファインダー機がフルサイズになったらもっと面白いことになりそうなので今は様子見でその先の楽しみにしたいと思っているところです。そん時いろいろ買い物ができるように考えておくと楽しいかもなぁ。
この前は撮影時にカメラを回転させたのか? と、思うくらいにグルグルボケしている画像をみつけましたが、なんとそれはシネカメラのレンズで、盛大にコマフレアが出ている画像でした。
新日本紀行のあのハロがたっぷり出ているけど情緒あふれる映像はNHKとキヤノンが協同で開発した8mmカメラのものだったとか、ググるといろんな情報が出てきます。
ニコンのカメラでFマウントの純正レンズ以外にも広大なレンズ沼が広がっているらしいです。
飲まれると死んでしまうこと確実だ。あぶないあぶない。
ということで、手が出せる範囲で楽しもうと思っています。
今撮影を楽しもうと思っているのが、前の投稿二つで使っている50mm f2 。
Nikkor-H C 50mm f2
開放で残る収差のバランスが絶妙で、独特の柔らかい画像が楽しめるらしいのです。シャープになるのはF4~5.6以上らしい。
欠点といわれるのはボケ玉の縁に濃いラインが現れることらしい。

この画像はf2.8。(ISO5000で、ノイズリダクションがOFFなのでザラザラです。前ピン状態で失敗ですけど)
2.8に一段絞るだけで周辺の暗さがなくなり均一な画像になる感じです。
遠くにあるイルミネーションとか、電照看板がしゃぼん玉みたいな縁取りになっています。
ですけど、このレンズの魅力はぼやけるでもなくぼけている背景とシャープなピント面の作る雰囲気です。点光源の大きいボケ玉を作らないようにすれば、欠点を発見されることもないでしょうし、夜景以外あまり気にしなくても良さそうです。
雰囲気の良さを活かした画像を沢山撮ってみたいです。
f1.4のレンズをあと二本。
Ai 35mm f1.4
このレンズのf1.4開放です。

このレンズの魅力は、f8位に絞ったときのシャープでカリッとした描写です。
ピントが良くて解像感があるので、中判でスナップするような、周囲を広く入れていろんなものを細かく見せるような作画ができそうで、楽しみです。
開けてボケを見せるようなものとはちょっと違う気がします。そのような使い方の出来る広角レンズもあるようですけど、「でも、お高いんでしょう?」なようです。
開放では、点光源の回りにはっきりと青いハロが出てきます。光源を写し込まなくても開放はふんわりしているようです。一段絞るだけで、スキッとなくなりシャープになります。
お次のf1.4は、
Ai 85mm f1.4
これの開放f1.4です。

これもいくぶんしゃぼん玉みたいな縁取りのあるボケ玉を作るみたいです。
105mmとかタムロンのSP90 マクロみたいな縁のないボケを持ってるレンズをそのうち手に入れたいです。
それはさておき、このレンズはニコンの85mmの中でも開放の柔らかさ(甘さとも言われているらしい)は一番良い(一番シャープじゃないとも言われるらしい)レンズらしいです。
Ai 85mm f2 も持ってるんですけど、確かにかっちりしたところを感じない甘い表現です。
しかーし、プラナー85mm f1.4 ZF のファインダー像(つまり開放)よりはくっきりはっきりしており、ピントの山も掴みやすいのは確かです。
でもまぁ、重箱の隅をつつくようなこういう話より、人間の目の世界にはない映画の中の世界のような表現を見せてくれるカメラの目を通して現実を写すのはとっても楽しい作業だと思うし、そうした画像を残すことは素敵なことだと思います。
これだって言えるような一枚をモノにしてみたいなぁと思うわけです。
↓Nikkor Ai 85mm f1.4 + D700 ISO800 1/80 F2.0

現代風にくっきり写るものも欲しいけど、ふんわりしっかり写るものも欲しかったんです。
それにしても、50年基本構造が変わらないというニコンのFマウントはすごいなと思います。
昔のレンズが今でも使えるからです。
マウント口径を大きく作ってあるキヤノンの一眼レフカメラにマウントアダプタを付けてニコンを始めさまざまなレンズが付けられるようで、これはこれで面白そうです。ペンタックスやミノルタの銘玉が使えるみたいだし、スクリューのライカなども付けているみたいです。
このあたりの楽しみというのは、その先リコーのGRなどレンジファインダー機がフルサイズになったらもっと面白いことになりそうなので今は様子見でその先の楽しみにしたいと思っているところです。そん時いろいろ買い物ができるように考えておくと楽しいかもなぁ。
この前は撮影時にカメラを回転させたのか? と、思うくらいにグルグルボケしている画像をみつけましたが、なんとそれはシネカメラのレンズで、盛大にコマフレアが出ている画像でした。
新日本紀行のあのハロがたっぷり出ているけど情緒あふれる映像はNHKとキヤノンが協同で開発した8mmカメラのものだったとか、ググるといろんな情報が出てきます。
ニコンのカメラでFマウントの純正レンズ以外にも広大なレンズ沼が広がっているらしいです。
飲まれると死んでしまうこと確実だ。あぶないあぶない。
ということで、手が出せる範囲で楽しもうと思っています。
今撮影を楽しもうと思っているのが、前の投稿二つで使っている50mm f2 。
Nikkor-H C 50mm f2
開放で残る収差のバランスが絶妙で、独特の柔らかい画像が楽しめるらしいのです。シャープになるのはF4~5.6以上らしい。
欠点といわれるのはボケ玉の縁に濃いラインが現れることらしい。

この画像はf2.8。(ISO5000で、ノイズリダクションがOFFなのでザラザラです。前ピン状態で失敗ですけど)
2.8に一段絞るだけで周辺の暗さがなくなり均一な画像になる感じです。
遠くにあるイルミネーションとか、電照看板がしゃぼん玉みたいな縁取りになっています。
ですけど、このレンズの魅力はぼやけるでもなくぼけている背景とシャープなピント面の作る雰囲気です。点光源の大きいボケ玉を作らないようにすれば、欠点を発見されることもないでしょうし、夜景以外あまり気にしなくても良さそうです。
雰囲気の良さを活かした画像を沢山撮ってみたいです。
f1.4のレンズをあと二本。
Ai 35mm f1.4
このレンズのf1.4開放です。

このレンズの魅力は、f8位に絞ったときのシャープでカリッとした描写です。
ピントが良くて解像感があるので、中判でスナップするような、周囲を広く入れていろんなものを細かく見せるような作画ができそうで、楽しみです。
開けてボケを見せるようなものとはちょっと違う気がします。そのような使い方の出来る広角レンズもあるようですけど、「でも、お高いんでしょう?」なようです。
開放では、点光源の回りにはっきりと青いハロが出てきます。光源を写し込まなくても開放はふんわりしているようです。一段絞るだけで、スキッとなくなりシャープになります。
お次のf1.4は、
Ai 85mm f1.4
これの開放f1.4です。

これもいくぶんしゃぼん玉みたいな縁取りのあるボケ玉を作るみたいです。
105mmとかタムロンのSP90 マクロみたいな縁のないボケを持ってるレンズをそのうち手に入れたいです。
それはさておき、このレンズはニコンの85mmの中でも開放の柔らかさ(甘さとも言われているらしい)は一番良い(一番シャープじゃないとも言われるらしい)レンズらしいです。
Ai 85mm f2 も持ってるんですけど、確かにかっちりしたところを感じない甘い表現です。
しかーし、プラナー85mm f1.4 ZF のファインダー像(つまり開放)よりはくっきりはっきりしており、ピントの山も掴みやすいのは確かです。
でもまぁ、重箱の隅をつつくようなこういう話より、人間の目の世界にはない映画の中の世界のような表現を見せてくれるカメラの目を通して現実を写すのはとっても楽しい作業だと思うし、そうした画像を残すことは素敵なことだと思います。
これだって言えるような一枚をモノにしてみたいなぁと思うわけです。
↓Nikkor Ai 85mm f1.4 + D700 ISO800 1/80 F2.0

2012年01月11日
誰でも引ける一番街のストリートピアノ
今日、一番街に行きました。ちょっとしたお手伝いで一瞬立ち寄ったという短い時間でしたけど。
今の中央駅が西鹿児島駅だったときから、西駅の一番街ってのは商店街でしたけど、ふるーいお店も軒をならべる昔ながらの商店街だったんですよね。
駅名が変わり、新幹線も通り、名実共に鹿児島の中央玄関になろうという時点で、一番街商店街も変身を図ろうとしている、なんつー話は聞いていたんですけど、行ったのは今日が初めて。
時間が速すぎて、お店はまだやってなかったんですけど。
アーケードになっていて通りも広く明るい感じ。雨の日でも安心。
ショッピングモールというのか、店舗が集合しているビルの前に小さな広場があって、そこにカラフルにペイントされたアップライトピアノがありました。
誰でも弾いていいストリートピアノなんだそうです。
ニュースで見たことあるような。

ピアノがバリバリ弾けるなら、リチャードクレーダーマンとか弾いてみたいな。
でも、ねこふんじゃったさえダメな自分なのでした。

いいなぁ。
今の中央駅が西鹿児島駅だったときから、西駅の一番街ってのは商店街でしたけど、ふるーいお店も軒をならべる昔ながらの商店街だったんですよね。
駅名が変わり、新幹線も通り、名実共に鹿児島の中央玄関になろうという時点で、一番街商店街も変身を図ろうとしている、なんつー話は聞いていたんですけど、行ったのは今日が初めて。
時間が速すぎて、お店はまだやってなかったんですけど。
アーケードになっていて通りも広く明るい感じ。雨の日でも安心。
ショッピングモールというのか、店舗が集合しているビルの前に小さな広場があって、そこにカラフルにペイントされたアップライトピアノがありました。
誰でも弾いていいストリートピアノなんだそうです。
ニュースで見たことあるような。

ピアノがバリバリ弾けるなら、リチャードクレーダーマンとか弾いてみたいな。
でも、ねこふんじゃったさえダメな自分なのでした。

いいなぁ。
2012年01月09日
鹿児島市護国神社の獅子舞
鹿児島のAMラジオ放送、南日本放送(MBC)で、桂竹丸さんが番組をやっています。面白いので良く聞くんです。うちの親がお友達から面白いよと勧められたらしくて、聞いてみたいといいだしました。
自分でラジオのスイッチが入れられないというほどの昔の人なので、聞けるようにセッティングして後は番組の時間にスイッチを入れるだけ。
放送時間の確認をしようと、MBCのHPで番組表を開きましたら、そこに護国神社の獅子舞の話題が載っていました。
http://blog.mbc.co.jp/takemaru/
このページの2012年1月のところ。
そうだ、この獅子舞の写真を撮ったんだったと思い出したので、今日はこの画像を貼ります。
護国神社には獅子舞の人が一人いて、舞ってくれるんですよ。
今年は出掛けませんでした。
考えてみると、私の生活は花鳥風月も春夏秋冬も関係のない無機質なものになってしまってる感じ。
季節の風物詩など、とんと無頓着になってしまっている。
子供の頃からそうなので、知らないこともいっぱいです。
来年のお正月はちゃんと計画でも立てて出掛けなきゃいけないかも。
さて、その記事、今年の獅子舞は高校三年の女の子が、ボーイスカウトの活動の一環としてボランティア活動でやっているとのことでした。
なーるほど、そうだったのか。
この獅子舞なるもの、(護国神社では?)獅子に手を噛んでもらったり頭をかじってもらったりすると、その一年が良いものになるという縁起物だったようです。
昨年は年末のあの大雪の中、弟の家族が鹿児島に帰省してきて、子供たちを初詣に連れて行くため、護国神社に出掛けたのでした。
そこで獅子舞を見ました。
一人でやってる獅子舞。その時は神社の若い氏子さんがやってるのかなぁと思ったけど、少年といっていいくらいの若い人に見えたのは、高校生だったからですね。
とっても利発そうな、気が利いてそうな人がしていて、獅子舞に寄ってくる人に、もれなく踊ってあげたり子供にはさらわせてあげたりしてた様子でした。それは、噛んでもらうといいことがあるという縁起担ぎがあるので、楽しみにやってきている人があぶれちゃわないよう気配りしてたんですね。ボーイスカウトをやるくらいだから、気が利いて見えるわけだ。
去年見たことを、今年納得したという私でした。

使用カメラ Nikon D80
レンズ Nikkor AF-S DX ED18-55/3.5-5.6G
ISO 640 1/200 f7.1
22mm位置で撮影、トリミングあり。変形その他レタッチあり
D50のレンズキットに付いてきたズームをD80で使っています。
昨年末他のボディーとレンズを買うまで、全部これで撮っています。
撮影もボタンを押すだけの全くの無頓着撮影。
AFはAF-CでONになっていますが、フォーカスポイントは画面中央になったままだからピンぼけです。

モノクロは好きです。
モノクロ人気がリバイバルしていると聞いたりしますけど、私にとって写真というのはもともとモノクロの存在なのであって、カラー写真は、{カラー} というプレミア扱いみたいな感じです。
子供の頃家にはオリンパスペンーEEというカメラがあって、家族でお出掛けするときは記念撮影のためにそれが持ち出されておりました。撮影した後残り枚数が0になるとシャッターが切れなくなるので、親がカメラごと写真屋さんへ持っていき、フイルムを交換してもらうという感じ。そのころはそれは親がやってることであって子供の私はあまり感知しない世界だった。フイルムは当然のように白黒。コニパンSS 16EX みたいな名前のものだった気がする。六枚撮り、12枚撮り、16、18枚撮り、20枚撮り、36枚撮りがあったような。
カラー写真というのは高級品で、フイルムの値段も高いし、現像に出すとこちら鹿児島から福岡まで送らないといけないとかで日にちもかかるしお金もかかるという代物だと聞かされてた気がします。
学生の頃自分で自家処理したこともありますが、当然白黒。
そのころ写真を友達にあげましたら、「なんだ白黒か」って言われたのを覚えています。そのころはカラーは富士カラーFIIというものだったと思います。ちょっと調べると、フジカラーF-IIは昭和49年発売らしい。それを何となく覚えています。ずっと後のHR100は粒状性がものすごく向上したみたいで、質感描写が良くなったこととコントラスト、色の濃さなど随分変わったなぁということを、こちらは良く覚えています。あまり書くと年の話になりそうなので、この辺にしておきます。

スナップ写真にしても、写真というのは人間関係が写るもんだということに最近気がつきまして、いい写真というのはいい関係のことでもあるらしいのですね。
私は引っ込み思案なので声をかけて撮るなんてのは考えられないわけです。
獅子舞も、他の人が舞ってもらってるのを横や後ろからついでに撮ってただけなんですけど、上に書いたように踊り手さんが写真撮ってる私に気をつかってくれて、私の真正面に来てポーズを撮ってくれたんですね。
弟家族のスナップなどを撮っているところだったわけです。D80はRAW記録で使用。クラス6のHDSDカードを使っておりまして、これだと連続で4枚撮ったところでバッファが一杯になるんです。いっぱいになった後カメラがSDへ書き込みを始めると、結構長い間操作を受け付けなくなります。獅子舞さんがポーズを撮ってくれたときこれに陥りまして、せっかく動きを止めてくれてるのにシャッター切れなくて焦るなぁって思って緊張しました。で、何とか一枚だけ撮れたのがこれです。
追記
ボーイスカウトでweb検索してみると、次のようなページが出てきました。
http://bsk18.blog19.fc2.com/blog-entry-32.html
http://www.geocities.jp/bs_kagoshima13/bsk18/bsk18top.html
http://bsk18.blog19.fc2.com/?mode=m&no=34
三つ目のページを読むと、護国神社の獅子は赤と緑の二匹がおり、夫婦獅子と呼ばれているらしいですね。すると、昨年私が見たのは夫の方で、今年MBCのサイトで見たのは奥さんだったのかしら?
自分でラジオのスイッチが入れられないというほどの昔の人なので、聞けるようにセッティングして後は番組の時間にスイッチを入れるだけ。
放送時間の確認をしようと、MBCのHPで番組表を開きましたら、そこに護国神社の獅子舞の話題が載っていました。
http://blog.mbc.co.jp/takemaru/
このページの2012年1月のところ。
そうだ、この獅子舞の写真を撮ったんだったと思い出したので、今日はこの画像を貼ります。
護国神社には獅子舞の人が一人いて、舞ってくれるんですよ。
今年は出掛けませんでした。
考えてみると、私の生活は花鳥風月も春夏秋冬も関係のない無機質なものになってしまってる感じ。
季節の風物詩など、とんと無頓着になってしまっている。
子供の頃からそうなので、知らないこともいっぱいです。
来年のお正月はちゃんと計画でも立てて出掛けなきゃいけないかも。
さて、その記事、今年の獅子舞は高校三年の女の子が、ボーイスカウトの活動の一環としてボランティア活動でやっているとのことでした。
なーるほど、そうだったのか。
この獅子舞なるもの、(護国神社では?)獅子に手を噛んでもらったり頭をかじってもらったりすると、その一年が良いものになるという縁起物だったようです。
昨年は年末のあの大雪の中、弟の家族が鹿児島に帰省してきて、子供たちを初詣に連れて行くため、護国神社に出掛けたのでした。
そこで獅子舞を見ました。
一人でやってる獅子舞。その時は神社の若い氏子さんがやってるのかなぁと思ったけど、少年といっていいくらいの若い人に見えたのは、高校生だったからですね。
とっても利発そうな、気が利いてそうな人がしていて、獅子舞に寄ってくる人に、もれなく踊ってあげたり子供にはさらわせてあげたりしてた様子でした。それは、噛んでもらうといいことがあるという縁起担ぎがあるので、楽しみにやってきている人があぶれちゃわないよう気配りしてたんですね。ボーイスカウトをやるくらいだから、気が利いて見えるわけだ。
去年見たことを、今年納得したという私でした。

使用カメラ Nikon D80
レンズ Nikkor AF-S DX ED18-55/3.5-5.6G
ISO 640 1/200 f7.1
22mm位置で撮影、トリミングあり。変形その他レタッチあり
D50のレンズキットに付いてきたズームをD80で使っています。
昨年末他のボディーとレンズを買うまで、全部これで撮っています。
撮影もボタンを押すだけの全くの無頓着撮影。
AFはAF-CでONになっていますが、フォーカスポイントは画面中央になったままだからピンぼけです。

モノクロは好きです。
モノクロ人気がリバイバルしていると聞いたりしますけど、私にとって写真というのはもともとモノクロの存在なのであって、カラー写真は、{カラー} というプレミア扱いみたいな感じです。
子供の頃家にはオリンパスペンーEEというカメラがあって、家族でお出掛けするときは記念撮影のためにそれが持ち出されておりました。撮影した後残り枚数が0になるとシャッターが切れなくなるので、親がカメラごと写真屋さんへ持っていき、フイルムを交換してもらうという感じ。そのころはそれは親がやってることであって子供の私はあまり感知しない世界だった。フイルムは当然のように白黒。コニパンSS 16EX みたいな名前のものだった気がする。六枚撮り、12枚撮り、16、18枚撮り、20枚撮り、36枚撮りがあったような。
カラー写真というのは高級品で、フイルムの値段も高いし、現像に出すとこちら鹿児島から福岡まで送らないといけないとかで日にちもかかるしお金もかかるという代物だと聞かされてた気がします。
学生の頃自分で自家処理したこともありますが、当然白黒。
そのころ写真を友達にあげましたら、「なんだ白黒か」って言われたのを覚えています。そのころはカラーは富士カラーFIIというものだったと思います。ちょっと調べると、フジカラーF-IIは昭和49年発売らしい。それを何となく覚えています。ずっと後のHR100は粒状性がものすごく向上したみたいで、質感描写が良くなったこととコントラスト、色の濃さなど随分変わったなぁということを、こちらは良く覚えています。あまり書くと年の話になりそうなので、この辺にしておきます。

スナップ写真にしても、写真というのは人間関係が写るもんだということに最近気がつきまして、いい写真というのはいい関係のことでもあるらしいのですね。
私は引っ込み思案なので声をかけて撮るなんてのは考えられないわけです。
獅子舞も、他の人が舞ってもらってるのを横や後ろからついでに撮ってただけなんですけど、上に書いたように踊り手さんが写真撮ってる私に気をつかってくれて、私の真正面に来てポーズを撮ってくれたんですね。
弟家族のスナップなどを撮っているところだったわけです。D80はRAW記録で使用。クラス6のHDSDカードを使っておりまして、これだと連続で4枚撮ったところでバッファが一杯になるんです。いっぱいになった後カメラがSDへ書き込みを始めると、結構長い間操作を受け付けなくなります。獅子舞さんがポーズを撮ってくれたときこれに陥りまして、せっかく動きを止めてくれてるのにシャッター切れなくて焦るなぁって思って緊張しました。で、何とか一枚だけ撮れたのがこれです。
追記
ボーイスカウトでweb検索してみると、次のようなページが出てきました。
http://bsk18.blog19.fc2.com/blog-entry-32.html
http://www.geocities.jp/bs_kagoshima13/bsk18/bsk18top.html
http://bsk18.blog19.fc2.com/?mode=m&no=34
三つ目のページを読むと、護国神社の獅子は赤と緑の二匹がおり、夫婦獅子と呼ばれているらしいですね。すると、昨年私が見たのは夫の方で、今年MBCのサイトで見たのは奥さんだったのかしら?
2012年01月09日
ブログ再再スタート
ブログを再再スタート。
更新が何度中断したかわからないくらいだけど、またスタートです。
この何年か、精神的にタフな期間でした。いろんなことに気がついて、重かったんです。
それをここに書いてもしょうがない気もするので、軽く書けそうな気がしたときには、そのことを書こうと思います。
ってなわけで、まぁ、再開。
画像貼り中心にやっていくと思います。

今日の画像は、旧の吉田町に最近できたと思われるデイケアセンターみたいなところの入り口に飾って? あったもの。
藁葺き屋根みたいな感じのもの。
大きさは60cm位の小ささ。
中に何が入ってるのかわからなかったけど。
格納するためのものなのか、ミニチュアで作った見本作品みたいなものなのか、一切不明ながら、手間がかかってそうな感じに引かれて写してみたものです。
カメラは以前から大好きでいじってますけど、最近入れ換えました。
本体はD700。今まで使っていたD80はAPS-CというDX規格。D700は35mmライカ判相当のFXフォーマット規格。昔の交換レンズが昔のままの画角で使えるというもの。
そして、D80よりは高級機種になるので、MFの昔のレンズも使えるようになっているというものです。何年も欲しかったけど、中古でようやく購入できました。
それならというわけで、昔のレンズだと現行のものより安く買えるということもあって、今回は50mmレンズを手に入れました。
ずっとD50と一緒に購入したキットレンズを使ってきましたので、別のものが欲しかったのです。
購入したレンズは、オートニッコール HC 50mm f2 というもの。30年以上前のもののようです。発売当初のママのものではなく、絞りリングがAi改造されているものです。なので、D700に付けると露出計が動くしAモードのオート撮影も可能です。
今回このレンズを購入したのにはわけがあるんです。
このニッコールの50mm f2 というレンズの評価がとても興味を引くものだったのです。
技術的なことはまったく理解していませんけども、何かの収差補正が完全ではなく、少し残されている設計になっているらしいのです。そのために、ニコンらしい「カタイ描写」をしないのだそうです。"ニコンらしくない柔らかい描写"とか"他のレンズより繊細な線の細い緻密な描写"だのと言われているらしいです。
古い黒沢映画を見るような雰囲気があるなどと言われているのもwebで見ました。
是非欲しいと思ったわけです。
一方で、ボケ玉の縁に濃い輪郭線がでる欠点があると指摘し、何度かのモデルチェンジで低分散ガラスまで採用されるほど手を入れられたにしては全く改善されなかった残念なものだと徹底的に悪い点を上げているサイトもあります。単コートがマルチコーティングになって低分散ガラスが入ってとすすむに連れ、シャドーがつぶれるニコンの描写になっていってるという批評もありましたから、昔のものであればある程よい描写をする可能性があるらしいのですね。
良く言っているサイトでは、「これは日本のズミクロンだ」とまで言われているところがあります。ライカのズミクロンには50mm f2 という全く同じスペックのものがあって画像も見てみましたが、ボケ玉の縁が濃い線でふちどりされるところもまるで同じでした。
でもまぁ、繊細な写りをするレンズではあるみたいです。
50mmはEM用の50mm f1.8 パンケーキスタイルというものも使って見ましたけど、言われているように線の太い硬い描写でした。f1.4は開放で柔らかいらしいけど、絞るほどニコンらしい描写へと大きく変わるらしいので、このf2はぜひ使って見たかったのです。50mm f2 はMF時代50mm f1.8 が出たことで販売が終了しているのでAFのGレンズの今の時代、中古でしか手に入らないMFレンズです。
長々書きましたけど、良いレンズらしいのは確かです。写真を撮るときには「本人の思い込み」こそが大事だと思うんです。
思い込みの上に思い込みを重ねていく作業が「クリエイト」する作業だと思えるフシがあるので、そこんところを大事にするというか、それをモチベーションにして自分で突き進まなきゃ、誰も背中を押してくれンだろうと、そう思うわけです。なので、思い込みのためのネタは、ぜひとも必要だったと、そういうわけです。
撮影データは
D700 Nikkor 50mm f2
ISO3200 1/2000秒 f4.0
この距離でf4だと、ピントは真ん中の屋根だけで前後は外れています。この感じをどう使うのかというあたりが50mmの難しさだろうけど、それはおいおい追求していこうかと思っている今日この頃です。
更新が何度中断したかわからないくらいだけど、またスタートです。
この何年か、精神的にタフな期間でした。いろんなことに気がついて、重かったんです。
それをここに書いてもしょうがない気もするので、軽く書けそうな気がしたときには、そのことを書こうと思います。
ってなわけで、まぁ、再開。
画像貼り中心にやっていくと思います。

今日の画像は、旧の吉田町に最近できたと思われるデイケアセンターみたいなところの入り口に飾って? あったもの。
藁葺き屋根みたいな感じのもの。
大きさは60cm位の小ささ。
中に何が入ってるのかわからなかったけど。
格納するためのものなのか、ミニチュアで作った見本作品みたいなものなのか、一切不明ながら、手間がかかってそうな感じに引かれて写してみたものです。
カメラは以前から大好きでいじってますけど、最近入れ換えました。
本体はD700。今まで使っていたD80はAPS-CというDX規格。D700は35mmライカ判相当のFXフォーマット規格。昔の交換レンズが昔のままの画角で使えるというもの。
そして、D80よりは高級機種になるので、MFの昔のレンズも使えるようになっているというものです。何年も欲しかったけど、中古でようやく購入できました。
それならというわけで、昔のレンズだと現行のものより安く買えるということもあって、今回は50mmレンズを手に入れました。
ずっとD50と一緒に購入したキットレンズを使ってきましたので、別のものが欲しかったのです。
購入したレンズは、オートニッコール HC 50mm f2 というもの。30年以上前のもののようです。発売当初のママのものではなく、絞りリングがAi改造されているものです。なので、D700に付けると露出計が動くしAモードのオート撮影も可能です。
今回このレンズを購入したのにはわけがあるんです。
このニッコールの50mm f2 というレンズの評価がとても興味を引くものだったのです。
技術的なことはまったく理解していませんけども、何かの収差補正が完全ではなく、少し残されている設計になっているらしいのです。そのために、ニコンらしい「カタイ描写」をしないのだそうです。"ニコンらしくない柔らかい描写"とか"他のレンズより繊細な線の細い緻密な描写"だのと言われているらしいです。
古い黒沢映画を見るような雰囲気があるなどと言われているのもwebで見ました。
是非欲しいと思ったわけです。
一方で、ボケ玉の縁に濃い輪郭線がでる欠点があると指摘し、何度かのモデルチェンジで低分散ガラスまで採用されるほど手を入れられたにしては全く改善されなかった残念なものだと徹底的に悪い点を上げているサイトもあります。単コートがマルチコーティングになって低分散ガラスが入ってとすすむに連れ、シャドーがつぶれるニコンの描写になっていってるという批評もありましたから、昔のものであればある程よい描写をする可能性があるらしいのですね。
良く言っているサイトでは、「これは日本のズミクロンだ」とまで言われているところがあります。ライカのズミクロンには50mm f2 という全く同じスペックのものがあって画像も見てみましたが、ボケ玉の縁が濃い線でふちどりされるところもまるで同じでした。
でもまぁ、繊細な写りをするレンズではあるみたいです。
50mmはEM用の50mm f1.8 パンケーキスタイルというものも使って見ましたけど、言われているように線の太い硬い描写でした。f1.4は開放で柔らかいらしいけど、絞るほどニコンらしい描写へと大きく変わるらしいので、このf2はぜひ使って見たかったのです。50mm f2 はMF時代50mm f1.8 が出たことで販売が終了しているのでAFのGレンズの今の時代、中古でしか手に入らないMFレンズです。
長々書きましたけど、良いレンズらしいのは確かです。写真を撮るときには「本人の思い込み」こそが大事だと思うんです。
思い込みの上に思い込みを重ねていく作業が「クリエイト」する作業だと思えるフシがあるので、そこんところを大事にするというか、それをモチベーションにして自分で突き進まなきゃ、誰も背中を押してくれンだろうと、そう思うわけです。なので、思い込みのためのネタは、ぜひとも必要だったと、そういうわけです。
撮影データは
D700 Nikkor 50mm f2
ISO3200 1/2000秒 f4.0
この距離でf4だと、ピントは真ん中の屋根だけで前後は外れています。この感じをどう使うのかというあたりが50mmの難しさだろうけど、それはおいおい追求していこうかと思っている今日この頃です。
2011年02月28日
ランニング桜島見ました
自分のブログのパスワードを忘れてしまうほど(ログインできなくて焦った)更新を止めてしまいましたが、再開です。
今日は突如時間が空いたので、ランニング桜島を見てきました。
参加人員が5000人を越す大きな大会でした。知り合いが出るという話だったので見に行ったのですけども、こんなに人が多いと全くわからない。とうとう最後まで会えずじまいでした。
大会の概要は鹿児島市の設置した大会HPに出ています。コースもグーグルマップへのリンクが出ていて詳細に見ることができます。5k、10k、ハーフと3つのクラスがあったみたいです。そのなかのハーフマラソンで今年はサプライズが。
コースを見てもらうとわかりますけど、メイン会場付近を走る5、10kと違い、(スタート、ゴール地点がある)は南方向だとすると、ハーフマラソンは桜島の火口から西方向へ伸びるコース。今日はそちら方面へ降灰があったようなのです。
ゴール付近で見ていると、顔がどす黒くなってる人が走ってきたりするんですけど、私は最初、デーモン小暮なみに受け狙いのメイクをして走ったものの、汗で流れたんだろうと思ったわけですが、何人も走ってくるうちにそれは「灰をかぶった」のだとわかりました。もう泥泥の人もいました。これは目が開けられないくらいつらかったかもよ?

今日は突如時間が空いたので、ランニング桜島を見てきました。
参加人員が5000人を越す大きな大会でした。知り合いが出るという話だったので見に行ったのですけども、こんなに人が多いと全くわからない。とうとう最後まで会えずじまいでした。
大会の概要は鹿児島市の設置した大会HPに出ています。コースもグーグルマップへのリンクが出ていて詳細に見ることができます。5k、10k、ハーフと3つのクラスがあったみたいです。そのなかのハーフマラソンで今年はサプライズが。
コースを見てもらうとわかりますけど、メイン会場付近を走る5、10kと違い、(スタート、ゴール地点がある)は南方向だとすると、ハーフマラソンは桜島の火口から西方向へ伸びるコース。今日はそちら方面へ降灰があったようなのです。
ゴール付近で見ていると、顔がどす黒くなってる人が走ってきたりするんですけど、私は最初、デーモン小暮なみに受け狙いのメイクをして走ったものの、汗で流れたんだろうと思ったわけですが、何人も走ってくるうちにそれは「灰をかぶった」のだとわかりました。もう泥泥の人もいました。これは目が開けられないくらいつらかったかもよ?

Posted by ひで at
00:20
│Comments(0)
2010年09月23日
川内大綱引を見てきました
川内大綱引を見てきました。
遅く出かけたので綱引きは見れず、着いたら終わっていましたが、余韻は楽しめました。
ぜひ来年みたいと思うところです。



http://satuma.homeip.net/weblog5/2010/09/2010.html
遅く出かけたので綱引きは見れず、着いたら終わっていましたが、余韻は楽しめました。
ぜひ来年みたいと思うところです。



http://satuma.homeip.net/weblog5/2010/09/2010.html
Posted by ひで at
21:13
│Comments(0)
2010年09月22日
ホンダ車三人組と接近遭遇しました
今日は、ホンダ車乗りの三人の若者と接近遭遇しました。

詳しい話は、別のブログに書き込むことにします。
別のブログはここです↓
http://satuma.homeip.net/weblog5/2010/09/post-38.html

詳しい話は、別のブログに書き込むことにします。
別のブログはここです↓
http://satuma.homeip.net/weblog5/2010/09/post-38.html
Posted by ひで at
03:46
│Comments(0)
2010年09月22日
うわー、統合失調症で発達障害で鬱全開かも~
久々の更新になります。
実は、私は脳の病気を持って生まれたらしいことを最近自覚しているところです。
治療が必要なほどひどいというわけではないかも知れんけど、いろいろ見聞きするところによると、統合失調症で発達障害で鬱を併発という感じらしい。
いくつもブログを始めては中断したり、システムを壊したり料金を払い忘れて消えたり、毎日のように更新してたかと思うとぷっつりやめたりというのは、これが原因になってるかもしれない。
そんなわけです。
そんなことを書こうと思ったのは、今日若者三人組と話したのがきっかけです。
そのことは、次のエントリーで。
実は、私は脳の病気を持って生まれたらしいことを最近自覚しているところです。
治療が必要なほどひどいというわけではないかも知れんけど、いろいろ見聞きするところによると、統合失調症で発達障害で鬱を併発という感じらしい。
いくつもブログを始めては中断したり、システムを壊したり料金を払い忘れて消えたり、毎日のように更新してたかと思うとぷっつりやめたりというのは、これが原因になってるかもしれない。
そんなわけです。
そんなことを書こうと思ったのは、今日若者三人組と話したのがきっかけです。
そのことは、次のエントリーで。
Posted by ひで at
03:26
│Comments(0)
2010年06月07日
ヴォルカの試合を見てきました。今年初黒星
ヴォルカ鹿児島の試合を見てきました。
県外にはなかなか見に行けないので今回の8,9節鹿児島集中開催は楽しみにしていたんです。
土曜日は先制されてからの逆転をどきどきしながら応援しました。
気をよくして日曜日、私は開始時間を間違えていて後半だけの観戦になりました。
昨日はドタバタしながらも山田選手が復帰後いきなりのゴールなどのいい材料があったなか、今日は更にドタバタしてしまったようで、相手の一点を返せずに試合終了。
あらら。HOYOにトップを明け渡して今年前半の終了。
しかし、いままでになく? 今年は強いヴォルカを堪能しまして満足している次第でございます。

ボールをはじいているとき目が開いている!

県外にはなかなか見に行けないので今回の8,9節鹿児島集中開催は楽しみにしていたんです。
土曜日は先制されてからの逆転をどきどきしながら応援しました。
気をよくして日曜日、私は開始時間を間違えていて後半だけの観戦になりました。
昨日はドタバタしながらも山田選手が復帰後いきなりのゴールなどのいい材料があったなか、今日は更にドタバタしてしまったようで、相手の一点を返せずに試合終了。
あらら。HOYOにトップを明け渡して今年前半の終了。
しかし、いままでになく? 今年は強いヴォルカを堪能しまして満足している次第でございます。

ボールをはじいているとき目が開いている!

Posted by ひで at
01:05
│Comments(0)
2010年06月05日
AKGのヘッドフォンにぶったまげた
AKGのヘッドフォン、K242HDを購入しました。
もう、ぶったまげました。
ちゃんとしたもの? は、やはりすごい。
とてもいい。
MDR-Z700DJがとてもいいと思っていたのに、上には上があるというか何というか。
ネットでいろんなレビューをみることができるので判断材料があるようでないのがヘッドフォンオーディオの世界かも。
今回も試聴の上購入しました。
ビックカメラに行ってみたら、ベスト電器にはないブランドがあったのです。AKGとゼンハイザー。
ベスト電器にもソニーやオーディオテクニカの7万円近いものの試聴コーナーがありましたけど、これはいつでもなっているわけではなくて、店員さんに断って鳴らしてもらわなければならないので買うかどうか決めていないのにそれをするのは敷居が高かったです。
ビックカメラでは三万円台のゼンハイザーとAKGが鳴っていました。
鳴っていましたと書きましたが行ったとき実は鳴っていなくて、試聴コーナーのDVDプレーヤーの電源スイッチを入り切りしたらなり出したのです。
早速聴いたわけですが高級品(~4万)はまったくぱっとしない音で、ほかのものを聴いていました。
今回これは良さそうだと思ったのがATH-M50でした。Z700DJ的な中音域の密度の高そうな音が印象的です。同じ傾向の音をナローレンジにしたような感じのものがパナソニックにあったのですが、これはなんと二千円台でした。
持っているATH-WS70もありましたので聴いたりして少し時間がたちました。
そして再び高い値段のところへ行って聴いてみると一台だけ耳を引く音のものがありました。それがK242HDです。ゼンハイザーはどれも魅力を感じないし、K530とK242HDが素直で実力があって上品な音のように思いまして、二つを比べると、242の方がワイドレンジな音で低音もしっかり鳴っている感じでした。
その試聴コーナーではどれも高音域が一本調子になっている気がしましたけど、たぶん、音源のプレーヤーがよくなかったのかもしれません。
少し時間をおいてからの高級品のなり方が違っていました。これはどういうことかあまりわからないのですけど、韓国製のDVDプレーヤーに原因があるのかも。このDVDプレーヤからテクニカの6か8出力のヘッドフォンアンプが数台(5,6台?)繋がっていましたので、かなり重い負荷になっているのかもしれません。
ともあれ、密度の高い音に感じたM50よりもK242が明るく繊細でのびのびしていて透明感のある高域と、はっきりした中音、しっかりした低音があるように思いました。なにしろ1万5千円クラスのヘッドホンがどれも似たような音がしているのに対し、K242はそれらの音から更にベールの2,3枚が一気にはがれる感じの音がするので、かなりなり方が違うことは確認できましたから思い切ってK242を購入しました。
買った後、自分のところで聴くと試聴の時よりずっといい音で鳴っていますし、エージング信仰者ではないけども、3日ほどたちましたけど荒い音ではなくなってきました。
iPhone直差し(オーディオテクニカのマイク付きの3極ー2極変換ケーブルを使用)ですが、びっくりの音質です。
低音最強と思っていたZ700DJよりしっかりした低音で、金物(シロフォンやトライアングルなど)がものすごく透明感のある美しい音でなります。
マラカスのような中音と高音の中間の帯域のような音がすごく大きく聞こえるような気がしましたが、いろいろな音源を聴くうちに、録音バランスとしてはK242で聞いている音がナチュラルであって、この帯域が引っ込んで聞こえるものしか持っていないからそう感じるのだろうと思いました。
ヘッドフォンのレビューをみていると、ロック向きクラッシック向きなどと分けているものが多いのですけど、それはおかしな話だと思っています。
ロックや歌謡曲、演歌にだってストリングスやオケの音が入っているのですしね。
なんでもちゃんとならすので、音源の違いをよく表現してくれますし、たぶんイコライザ、低音高音の音質調整ツマミにも敏感なタイプだとおもいます。フラットでワイドレンジでバランスのとれたものはそういうものなので、iPhoneには調整がないけど、そう感じます。
いままで持っていたヘッドフォンではバスドラとベースの聞き分けなど、耳を澄まして聞き分けるようなことをしていたわけですけど、そんなことをまるでしなくても、ただ普通に聴いていて余裕で鳴らし分けてくれています。
情報力が多くて聴いてて楽しいです。
仕事帰りの車で聴くことが多いのですけど、あまりに楽しいので車を止めてアルバムを一枚聴いてしまってから帰る、などということまでしちゃうほどです。
とにかく上には上があるんだと思い知らされたヘッドフォンです。
これを聴いてからわかるようになりました。ATH-WS70は低音の凸凹が大きくてバスドラが引っ込んでしまう傾向があるのに加え、ボーカルの声量感がない代わりに、4K前後のカンカンするくらいのところになにか共振があるみたいで、声量感を感じたいのでボリュームを上げて聴くと、カンカンする帯域の音がものすごく大きく鳴ってしまっていて、しばらく聴いていると耳がとても疲れます。聴き疲れするので、ボリュームのあげすぎには注意です。ソニーのXB700も低音の質こそ違うのだけど、バスドラが引っ込んで聞こえる凸凹と、中音の共振の感じがWS70より下と、さらに高域のところにあってとても癖のある音です。イヤホンからの移行だとかなりワイドになるので幸せになれそうなんですが、もう少し出費覚悟でM50やZ700DJのほうが聴き疲れしなくて良さそうです。
K242HDは音源の音質の違いまではっきりわかるようなすばらしさ+音楽を聴く楽しみがあって、値段の分の価値はあるとおもいました。音量を上げて聴いても、WS70のように聴き疲れして、聴き終わってからキーンと耳鳴りがするなんてこともないのです。
K242HDを知ってみると、ヘッドフォンに数万出すなんてことが破天荒の散財などではないことがわかると、ほかのものもすごく気になるようになってきました。
3万5千円ほどで購入しましたが、ネットの最安値では2万で買えるところがあるようです。
すごい値段の違いです。、でもネットの最大のネックは試聴して買えないことです。
オーディオ製品ばかりは試聴しないと、値段と音質が全く関連性がないので怖いです。二千円のものが楽しく聴けそうな感じがしたり、4万のものでも聴いてて楽しくなさそうだったり平気でするからです。
一万5千円くらい余計な出費だったけど、試聴して判断できる安心料だという気もします。
なにはともあれヘッドフォンスパイラルにはまってしまいました。
もう、ぶったまげました。
ちゃんとしたもの? は、やはりすごい。
とてもいい。
MDR-Z700DJがとてもいいと思っていたのに、上には上があるというか何というか。
ネットでいろんなレビューをみることができるので判断材料があるようでないのがヘッドフォンオーディオの世界かも。
今回も試聴の上購入しました。
ビックカメラに行ってみたら、ベスト電器にはないブランドがあったのです。AKGとゼンハイザー。
ベスト電器にもソニーやオーディオテクニカの7万円近いものの試聴コーナーがありましたけど、これはいつでもなっているわけではなくて、店員さんに断って鳴らしてもらわなければならないので買うかどうか決めていないのにそれをするのは敷居が高かったです。
ビックカメラでは三万円台のゼンハイザーとAKGが鳴っていました。
鳴っていましたと書きましたが行ったとき実は鳴っていなくて、試聴コーナーのDVDプレーヤーの電源スイッチを入り切りしたらなり出したのです。
早速聴いたわけですが高級品(~4万)はまったくぱっとしない音で、ほかのものを聴いていました。
今回これは良さそうだと思ったのがATH-M50でした。Z700DJ的な中音域の密度の高そうな音が印象的です。同じ傾向の音をナローレンジにしたような感じのものがパナソニックにあったのですが、これはなんと二千円台でした。
持っているATH-WS70もありましたので聴いたりして少し時間がたちました。
そして再び高い値段のところへ行って聴いてみると一台だけ耳を引く音のものがありました。それがK242HDです。ゼンハイザーはどれも魅力を感じないし、K530とK242HDが素直で実力があって上品な音のように思いまして、二つを比べると、242の方がワイドレンジな音で低音もしっかり鳴っている感じでした。
その試聴コーナーではどれも高音域が一本調子になっている気がしましたけど、たぶん、音源のプレーヤーがよくなかったのかもしれません。
少し時間をおいてからの高級品のなり方が違っていました。これはどういうことかあまりわからないのですけど、韓国製のDVDプレーヤーに原因があるのかも。このDVDプレーヤからテクニカの6か8出力のヘッドフォンアンプが数台(5,6台?)繋がっていましたので、かなり重い負荷になっているのかもしれません。
ともあれ、密度の高い音に感じたM50よりもK242が明るく繊細でのびのびしていて透明感のある高域と、はっきりした中音、しっかりした低音があるように思いました。なにしろ1万5千円クラスのヘッドホンがどれも似たような音がしているのに対し、K242はそれらの音から更にベールの2,3枚が一気にはがれる感じの音がするので、かなりなり方が違うことは確認できましたから思い切ってK242を購入しました。
買った後、自分のところで聴くと試聴の時よりずっといい音で鳴っていますし、エージング信仰者ではないけども、3日ほどたちましたけど荒い音ではなくなってきました。
iPhone直差し(オーディオテクニカのマイク付きの3極ー2極変換ケーブルを使用)ですが、びっくりの音質です。
低音最強と思っていたZ700DJよりしっかりした低音で、金物(シロフォンやトライアングルなど)がものすごく透明感のある美しい音でなります。
マラカスのような中音と高音の中間の帯域のような音がすごく大きく聞こえるような気がしましたが、いろいろな音源を聴くうちに、録音バランスとしてはK242で聞いている音がナチュラルであって、この帯域が引っ込んで聞こえるものしか持っていないからそう感じるのだろうと思いました。
ヘッドフォンのレビューをみていると、ロック向きクラッシック向きなどと分けているものが多いのですけど、それはおかしな話だと思っています。
ロックや歌謡曲、演歌にだってストリングスやオケの音が入っているのですしね。
なんでもちゃんとならすので、音源の違いをよく表現してくれますし、たぶんイコライザ、低音高音の音質調整ツマミにも敏感なタイプだとおもいます。フラットでワイドレンジでバランスのとれたものはそういうものなので、iPhoneには調整がないけど、そう感じます。
いままで持っていたヘッドフォンではバスドラとベースの聞き分けなど、耳を澄まして聞き分けるようなことをしていたわけですけど、そんなことをまるでしなくても、ただ普通に聴いていて余裕で鳴らし分けてくれています。
情報力が多くて聴いてて楽しいです。
仕事帰りの車で聴くことが多いのですけど、あまりに楽しいので車を止めてアルバムを一枚聴いてしまってから帰る、などということまでしちゃうほどです。
とにかく上には上があるんだと思い知らされたヘッドフォンです。
これを聴いてからわかるようになりました。ATH-WS70は低音の凸凹が大きくてバスドラが引っ込んでしまう傾向があるのに加え、ボーカルの声量感がない代わりに、4K前後のカンカンするくらいのところになにか共振があるみたいで、声量感を感じたいのでボリュームを上げて聴くと、カンカンする帯域の音がものすごく大きく鳴ってしまっていて、しばらく聴いていると耳がとても疲れます。聴き疲れするので、ボリュームのあげすぎには注意です。ソニーのXB700も低音の質こそ違うのだけど、バスドラが引っ込んで聞こえる凸凹と、中音の共振の感じがWS70より下と、さらに高域のところにあってとても癖のある音です。イヤホンからの移行だとかなりワイドになるので幸せになれそうなんですが、もう少し出費覚悟でM50やZ700DJのほうが聴き疲れしなくて良さそうです。
K242HDは音源の音質の違いまではっきりわかるようなすばらしさ+音楽を聴く楽しみがあって、値段の分の価値はあるとおもいました。音量を上げて聴いても、WS70のように聴き疲れして、聴き終わってからキーンと耳鳴りがするなんてこともないのです。
K242HDを知ってみると、ヘッドフォンに数万出すなんてことが破天荒の散財などではないことがわかると、ほかのものもすごく気になるようになってきました。
3万5千円ほどで購入しましたが、ネットの最安値では2万で買えるところがあるようです。
すごい値段の違いです。、でもネットの最大のネックは試聴して買えないことです。
オーディオ製品ばかりは試聴しないと、値段と音質が全く関連性がないので怖いです。二千円のものが楽しく聴けそうな感じがしたり、4万のものでも聴いてて楽しくなさそうだったり平気でするからです。
一万5千円くらい余計な出費だったけど、試聴して判断できる安心料だという気もします。
なにはともあれヘッドフォンスパイラルにはまってしまいました。
Posted by ひで at
02:27
│Comments(0)
2010年05月31日
ヘッドホンをもう一つ購入
ATH-WS70でバスドラが聞こえにくいことに気が付いてから、他のものが気になりだし、臨時収入があったので一本購入することにしました。
前に書いた試聴コーナーに出向き、バスドラとベースの音がちゃんと分かれて聞こえるものを改めて選んでみようと思いました。
ライバルと言われるXB700を聞き、ATHA700 ATHAD700、900と聞き比べてみました。オーディオテクニカの上級機とWS70とも聞き比べながら音の傾向を探ってみました。さすがに上級機はバスドラがちゃんと聞こえるけども、WS70は聞こえにくいという傾向がはっきりわかりました。
ソニーのXB700はブーミーな低音ではあるのですが、ソニーの上級機と聞き比べてみるとテクニカと同じようにバスドラが出て聞こえてきます。音の傾向は上級機もブーミーです。WS70よりXB700はブーミーなんですが意外なことに、バスドラが上級機より引っ込んで聞こえるという傾向は同じなんです。
WS70と思いっきり違う傾向の音でもいいからバスドラとベースがちゃんと分かれて聞こえるものという点で、MDR-Z700DJという機種がありました。中音域が大きく、高音域はあまり出ていない感じです。出ていないけれども、音の傾向は素直です。
WS70はワイドレンジ風だけど線の細い感じ、テクニカの上級機と共通しているのは高音域が綺麗な響きです。低域は迫力あるけど締まっています。
XB700はブーミーだけど低域は出ています。中域も力強くてテクニカとは違う特徴があるのですが、広域に特有のピーク感がある感じです。レビューで見かける「さ行強調系の音が耳に刺さる」というサウンドになりやすそうです。特に、FM放送などで聞かれる故障じゃないかというくらいさ行が強調されるあの音を再生したら厳しいかもしれません。
MDRZ700DJが、一番バスドラとベースの音がちゃんと区別できてしっかり鳴る感じの音でした。
高音が出ていない感じなんですけど、一切のカラーリングがないなり方です。こんな高域のほうが、たとえばシンバルのメーカーと品番を音だけで言い当てるようなテスト? はやりやすいはずです。バスドラの帯域がちゃんと出て低音がしっかりしていて中域の密度が濃いけど高域がちょっと物足りないという、WS70とは全然違うこれを1万6000円程で購入。
早速iPhoneに差し、帰りの車の中で聞きました。
驚いたことに、ひこうき雲のバスドラがはっきり聞こえます。こんなに大きく鳴ってるのになんで聞こえなかったのか、というくらい。
別なものを聞いて気がつきましたが、ハンドクラップの時、ボーカルの破裂音、歌いだしなどでポップノイズが入っているものがありました。中にはマイクスタンドに何かぶつけたような音が聞こえるものも。
PX200で聞こえたヒスノイズもちゃんと聞こえるし、分解能が高くていい感じです。
しかし、これらの音が聞こえないまま平気だったのかといまさら驚く感じ。
聞いていて一番いい点は、バランス的に超ドストライクな音を聞いている感じがして安心できることです。
なんといっても一番いいのはスネアの音が生のバランスに近く聞こえることです。イヤフォンなどではスネアが鳴ってるのかシンバルかわからないなり方のものも多いんですけど、Z700DJは太鼓音とスネアがミックスされたスネア音でなります。ドラムセット全体がバランス良く聞こえるようになりました。
ポップスはバスドラとベースが同時になるので、バスドラが聞こえなくてもベースが聞こえればリズム的なバランスは崩れずに聞こえるのでWS70でも良かったのかもしれません。それに、新しい録音はバスドラが聞きやすく処理されているから、なおさら気にならなかったのかもしれません。
改めて聞き比べても、ピアノの響きの美しさや弦楽器の楽しさは断然こちらがありますし、全部の音が一つの空間にまとまる楽しさはこちらにあります。
一方、Z700DJはモニター的サウンドで、つい細部を聞き込んでしまいます。いろんな発見があって面白いのですが聞いて楽しいかというと楽しくない気がします。音色的な美点がないからです。これがあるとモニターにならないのでまじめな製品なんだと思います。楽しむ目的には全く向かないから売れるんだろうかという気がするけども、モニターユースには帯域的にもカラーリングのなさからもこの製品には絶対的ニーズはありそうだと思います。量的には少ないんだろうけどちゃんとラインナップするというところはソニーは良心的メーカーなのかなと思いました。
取り替えながら聴く楽しみが増えた感じです。
前に書いた試聴コーナーに出向き、バスドラとベースの音がちゃんと分かれて聞こえるものを改めて選んでみようと思いました。
ライバルと言われるXB700を聞き、ATHA700 ATHAD700、900と聞き比べてみました。オーディオテクニカの上級機とWS70とも聞き比べながら音の傾向を探ってみました。さすがに上級機はバスドラがちゃんと聞こえるけども、WS70は聞こえにくいという傾向がはっきりわかりました。
ソニーのXB700はブーミーな低音ではあるのですが、ソニーの上級機と聞き比べてみるとテクニカと同じようにバスドラが出て聞こえてきます。音の傾向は上級機もブーミーです。WS70よりXB700はブーミーなんですが意外なことに、バスドラが上級機より引っ込んで聞こえるという傾向は同じなんです。
WS70と思いっきり違う傾向の音でもいいからバスドラとベースがちゃんと分かれて聞こえるものという点で、MDR-Z700DJという機種がありました。中音域が大きく、高音域はあまり出ていない感じです。出ていないけれども、音の傾向は素直です。
WS70はワイドレンジ風だけど線の細い感じ、テクニカの上級機と共通しているのは高音域が綺麗な響きです。低域は迫力あるけど締まっています。
XB700はブーミーだけど低域は出ています。中域も力強くてテクニカとは違う特徴があるのですが、広域に特有のピーク感がある感じです。レビューで見かける「さ行強調系の音が耳に刺さる」というサウンドになりやすそうです。特に、FM放送などで聞かれる故障じゃないかというくらいさ行が強調されるあの音を再生したら厳しいかもしれません。
MDRZ700DJが、一番バスドラとベースの音がちゃんと区別できてしっかり鳴る感じの音でした。
高音が出ていない感じなんですけど、一切のカラーリングがないなり方です。こんな高域のほうが、たとえばシンバルのメーカーと品番を音だけで言い当てるようなテスト? はやりやすいはずです。バスドラの帯域がちゃんと出て低音がしっかりしていて中域の密度が濃いけど高域がちょっと物足りないという、WS70とは全然違うこれを1万6000円程で購入。
早速iPhoneに差し、帰りの車の中で聞きました。
驚いたことに、ひこうき雲のバスドラがはっきり聞こえます。こんなに大きく鳴ってるのになんで聞こえなかったのか、というくらい。
別なものを聞いて気がつきましたが、ハンドクラップの時、ボーカルの破裂音、歌いだしなどでポップノイズが入っているものがありました。中にはマイクスタンドに何かぶつけたような音が聞こえるものも。
PX200で聞こえたヒスノイズもちゃんと聞こえるし、分解能が高くていい感じです。
しかし、これらの音が聞こえないまま平気だったのかといまさら驚く感じ。
聞いていて一番いい点は、バランス的に超ドストライクな音を聞いている感じがして安心できることです。
なんといっても一番いいのはスネアの音が生のバランスに近く聞こえることです。イヤフォンなどではスネアが鳴ってるのかシンバルかわからないなり方のものも多いんですけど、Z700DJは太鼓音とスネアがミックスされたスネア音でなります。ドラムセット全体がバランス良く聞こえるようになりました。
ポップスはバスドラとベースが同時になるので、バスドラが聞こえなくてもベースが聞こえればリズム的なバランスは崩れずに聞こえるのでWS70でも良かったのかもしれません。それに、新しい録音はバスドラが聞きやすく処理されているから、なおさら気にならなかったのかもしれません。
改めて聞き比べても、ピアノの響きの美しさや弦楽器の楽しさは断然こちらがありますし、全部の音が一つの空間にまとまる楽しさはこちらにあります。
一方、Z700DJはモニター的サウンドで、つい細部を聞き込んでしまいます。いろんな発見があって面白いのですが聞いて楽しいかというと楽しくない気がします。音色的な美点がないからです。これがあるとモニターにならないのでまじめな製品なんだと思います。楽しむ目的には全く向かないから売れるんだろうかという気がするけども、モニターユースには帯域的にもカラーリングのなさからもこの製品には絶対的ニーズはありそうだと思います。量的には少ないんだろうけどちゃんとラインナップするというところはソニーは良心的メーカーなのかなと思いました。
取り替えながら聴く楽しみが増えた感じです。
Posted by ひで at
23:49
│Comments(0)
2010年05月28日
ブラウン管の次に消えるべきなのはムービングコイル
ヘッドフォンで聞くiPhoneに感動し、勢いでポストしたので推敲せねばと思う一つ前のエントリー。ちゃんと推敲するためには適当に書いていた機種名を見てこないといけない。
そんなわけで、かの試聴コーナーに再び出かけて写メを撮ってきました。店員に怪しまれることなく、無事完了。
取りかかる前に、音の表現方法の言葉を知らなければいけないと思ってネットの記事をいくつか見ておかねばと思った。
で、型番で出てきた最初のページを見たのですが、予想外のことが書いてあるので考え込んでしまいました。
http://review.kakaku.com/review/K0000063730/
アマゾンのカスタマーレビューはおおむね気に入ってる人が推薦している感じで、それには同意できました。
びっくりしたのが価格コムの口コミ掲示板。ATH-WS70を、低音が出ないと言ってる人がいるのです。XB700の方が低音が出ると書いてあるものがいくつか。
この中に出てくる、ソニーのXB700は試聴したものの中にあったので、音もわかります。
ATH-WS70とは全く違った傾向の音。二つの音の違いも自分の中ではっきりしている。
XB700は音像は固まっていて、音場感という言い方をすると広がらない感じ。主に低音がブーミーななり方をしているからなおさらそう感じた。確かに音程感のある200Hz位のところはATH-WS70より景気よく出ている気がする。しかし、そのずっと下の、音程感のなくなる100Hzより下のところの低音は確実にATH-WS70のほうがしっかり出ているし、もっと下の帯域が持ち上がっているのか、ホールの鳴りというか空間の鳴りみたいなものが感じられて迫力がある。
まず、ATH-WS70の優れているところ。
XB700とATH-WS70の音は前者がウォーム系で後者がクール系なんだとおもうけども、なんといっても後者の方がリニアリティー(強弱に対する再現能力の高さ)が断然優れていて、上級クラスのヘッドフォンを凌駕するのではという感じがする。
ONに録られた音源とOFF気味でプレゼンス感たっぷりの音源が重ねられているような昔のポップスやドラムスが入ったクラッシックのメドレーみたいなものでも楽しく聞ける。リニアリティーが良くないイヤフォンで聞くCDのなかには、頭の中のあちらこちらでバラバラに音が鳴っていたり、やたら遠いオケの伴奏に、エコー無しの生ボーカルが歌うような違和感のある音楽に聞こえたりするものがあるのですけど、そういうCDでも、楽しくひとまとまりの音楽として楽しめるのが、このATH-WS70です。
音楽として聞く楽曲は必ずエコー処理されているものですけど、そのエコーの流れる方向や広がり方がしっかり確認できるのも、リニアリティーに優れている証拠だと思います。
さて、このヘッドフォンのレビューで「低音が不足している」と言い出す(そう聞こえる)人がいるのを知って、改めてはっと思ったことがあります。
それはスピーカーシステムでいう、「バスレフのチューニング」です。
現在のスピーカーは、ほとんど全部がムービングコイル式。これは、磁界の中においたコイルに電流を流すと力学的な力が発生するという現象を利用したもの。モーターが回るのもこの理屈。モーターは電力を与えると際限なく回ります。ムービングコイルも同じで、電力が与えられたら動くんですけど、バネがついていて、電力による力とバネの力が均衡する位置まで動くと止まるし、電力がなくなるとバネが元の位置に引き戻すようにできている。バネが入った系なんですが、このことによって共振現象というものがついて回ることになり、話をはしょると、スピーカーには最低共振周波数というものが存在することになると言うことです。電気的にはその周波数でインピーダンスが上昇することになり、インピーダンスが上昇すると言うことは現在の回路のアンプでは電力が供給しにくくなると言うことになり、結局の話スピーカーが低音を出しにくいのは原理的なことが原因という話なんです。
その最低共振周波数というのは100Hz前後のものが多かったりしますから、世の中のスピーカーというもので音楽の低音を楽しもうと思ったら、一ひねりもふたひねりもしてある製品でなければムリ、という仕組みになっていたりします。
スピーカーユニットを密閉式の箱に入れてスピーカーシステムを作り、周波数特性を取ると、なだらかに低音にいくに従って音が小さくなる特性になるものが多く、それを改善するための一つがバスレフシステムというものです。これは、箱に低音の共振を持たせたものです。ギターの胴も共鳴箱ですけども、ギターの箱の共鳴は割と幅広い周波数で共鳴するように作られているのに対し、バスレフスピーカーは特定の音にだけ共鳴するように作られます。スピーカーユニットの最低共振周波数とその箱とのかんけいで、なだらかに低音が出にくくなる密閉箱よりも、フラットな特性の低音が出せるようになるのですけど、あるところでストンと落ちる特性になります。バスレフの共鳴周波数をもっと下げると、もっと低いところまで低音が出せるようにチューニング出来まが、広がる手前の(上の)周波数のところに、くぼみが出来ます(鳴りにくいところが出来る)。くぼみが出来ても、低いところまで鳴るようになって迫力が得られたら成功だし、かえってそれで低音の量感が不足してしまうこともあり得て、これは実際にテストしてほどよいところを探る、なんてことが行われたりします。
これを高度に複雑に行ったものがBOSEのアコースティックなんとかシステムというもので、びっくりするほど迫力ある低音が出るのだけど、ふくよかななりの低音楽器のニュアンスは出せなかったりすると言う、まぁ、そんなものもあります。
これはムービングコイル方式のスピーカーを使う以上はずっとこんな調子なんだろうと思います。
エジソンからちょっとあとずっと続いているわけです。
ブラウン管はようやく最近製造中止になりました。
次はムービングコイル式のスピーカーの代わりになる何かが発明される番だと思います。スタックスの静電式というものが古くからありますけどドライブユニットが特殊で高価なせいか全く普及してる様子はないようです。
で、話が脱線しましたけど、ATH-WS70も、バスレフ式のスピーカーユニットの話と同じような感じの低音であることは感じていたので、「低音が不足している」と書いた人がいると言うことは、これに関係しているのかもしれないと思いました。
そして、ソース(聞いたCD)はなんなのか気になるところです。
ATH-WS70はソリッドベースシステムというユニットの後ろ側に共鳴空間があって低音が強調されているという話なので、聞こえにくい(窪んだ帯域)周波数が出来てしまっているのかもしれません。そこの部分の音が入っているCDを普段聞いている人がこのヘッドフォンを使ってしまったのかもしれないと思うと、あり得る話です。
で、ATH-WS70を使って、「荒井由実」の「ひこうき雲」を聞いていたときに、バスドラが聞こえにくいということを発見。このアルバムは元々バスドラは小さな音で聞こえます。このアルバムに限らず、低音域がタイトな音で収録されているCDを十分な低音間で再生できる装置というのはあまりない気がします。ビリージョエルの最初の方のものも低音の録音技術は優れている(低い音までしっかり録られている)けども、響きがタイトなので装置を選ぶ気がします。ひこうき雲を収録したのはスタジオアルファで、ここの録音もアナログ時代にしてはタイトなドラムだったようで、この辺の事情があるのか(聞く装置しだいでしっかり響く低音なのかもしれん)、とにかくひこうき雲のバスドラは、私には小さく聞こえています。(アルファスタジオは埋め込みのツインウーファーがモニターで、ドラムのブースは石畳になっていたとかで、録られた音を聞いていて個性的に感じるけどもそれは録音エンジニアにもそれなりの何かポリシーがあるんだと思う。これはこれで調べてみるとおもしろいかもしれないけどはまり込みそうだからしない笑)
そのひこうき雲のバスドラがATH-WS70で聞こえない場面がほとんどになってしまっています。
試しにビクターのNC80につなぎ替えて聞いてみると、なんと、聞こえるではあーりませんか。
うーむ。
これはどうしたもんか。
チューニングをが変わった次モデルが出るのか期待することにしようっと。
バスレフのチューニングのような共鳴系の音というのは、共振Qというものがとても高いので、1/3オクターブバンドのグライコみたいなものでは、上の窪んだ帯域を持ち上げるなんてことはちょっとムリです。Qを可変することが可能なパラメトリックイコライザーでも、かなり極端な設定にしないといけないはずだし、悪影響もあると思います。特定のCDを聞くために割り切ってそれをやってみることもおもしろいかもしれませんが、数十万しそうな機械を7000円で購入できる装着感のきついATH-WS70でやるのも現実味がないですよね。
まあしかし、聞こえるものが聞こえない今回のパターンは特別な例だとおもわれます。
ATH-WS70の迫力低音はこれはこれでおもしろいし、今のところ私には空間構成力と名付けられるかもしれないこのヘッドフォンの能力は、いろんな音楽を楽しく聴かせてくれる存在ではあります。弦楽器がリアルだしなんといってもピアノが軽やかに鳴って鳴ってくれるのが嬉しいです。
クラッシックも楽しいです。低音強調がちょっと大げさで、クラッシックの場合コントラバスがこんなに鳴り響いているホールなんてあり得んと思いつつも、脳内補正しつつ聞いてしまうと言うわけです。(ATH-WS70のひこうき雲ではフロアタムの音があり得なく大きく聞こえますけど、MP-NC80ではバランスの取れた音量で聞こえます。ATH-WS70はバスドラが消えて、フロアタムがでかく聞こえる)
そんなわけで、かの試聴コーナーに再び出かけて写メを撮ってきました。店員に怪しまれることなく、無事完了。
取りかかる前に、音の表現方法の言葉を知らなければいけないと思ってネットの記事をいくつか見ておかねばと思った。
で、型番で出てきた最初のページを見たのですが、予想外のことが書いてあるので考え込んでしまいました。
http://review.kakaku.com/review/K0000063730/
アマゾンのカスタマーレビューはおおむね気に入ってる人が推薦している感じで、それには同意できました。
びっくりしたのが価格コムの口コミ掲示板。ATH-WS70を、低音が出ないと言ってる人がいるのです。XB700の方が低音が出ると書いてあるものがいくつか。
この中に出てくる、ソニーのXB700は試聴したものの中にあったので、音もわかります。
ATH-WS70とは全く違った傾向の音。二つの音の違いも自分の中ではっきりしている。
XB700は音像は固まっていて、音場感という言い方をすると広がらない感じ。主に低音がブーミーななり方をしているからなおさらそう感じた。確かに音程感のある200Hz位のところはATH-WS70より景気よく出ている気がする。しかし、そのずっと下の、音程感のなくなる100Hzより下のところの低音は確実にATH-WS70のほうがしっかり出ているし、もっと下の帯域が持ち上がっているのか、ホールの鳴りというか空間の鳴りみたいなものが感じられて迫力がある。
まず、ATH-WS70の優れているところ。
XB700とATH-WS70の音は前者がウォーム系で後者がクール系なんだとおもうけども、なんといっても後者の方がリニアリティー(強弱に対する再現能力の高さ)が断然優れていて、上級クラスのヘッドフォンを凌駕するのではという感じがする。
ONに録られた音源とOFF気味でプレゼンス感たっぷりの音源が重ねられているような昔のポップスやドラムスが入ったクラッシックのメドレーみたいなものでも楽しく聞ける。リニアリティーが良くないイヤフォンで聞くCDのなかには、頭の中のあちらこちらでバラバラに音が鳴っていたり、やたら遠いオケの伴奏に、エコー無しの生ボーカルが歌うような違和感のある音楽に聞こえたりするものがあるのですけど、そういうCDでも、楽しくひとまとまりの音楽として楽しめるのが、このATH-WS70です。
音楽として聞く楽曲は必ずエコー処理されているものですけど、そのエコーの流れる方向や広がり方がしっかり確認できるのも、リニアリティーに優れている証拠だと思います。
さて、このヘッドフォンのレビューで「低音が不足している」と言い出す(そう聞こえる)人がいるのを知って、改めてはっと思ったことがあります。
それはスピーカーシステムでいう、「バスレフのチューニング」です。
現在のスピーカーは、ほとんど全部がムービングコイル式。これは、磁界の中においたコイルに電流を流すと力学的な力が発生するという現象を利用したもの。モーターが回るのもこの理屈。モーターは電力を与えると際限なく回ります。ムービングコイルも同じで、電力が与えられたら動くんですけど、バネがついていて、電力による力とバネの力が均衡する位置まで動くと止まるし、電力がなくなるとバネが元の位置に引き戻すようにできている。バネが入った系なんですが、このことによって共振現象というものがついて回ることになり、話をはしょると、スピーカーには最低共振周波数というものが存在することになると言うことです。電気的にはその周波数でインピーダンスが上昇することになり、インピーダンスが上昇すると言うことは現在の回路のアンプでは電力が供給しにくくなると言うことになり、結局の話スピーカーが低音を出しにくいのは原理的なことが原因という話なんです。
その最低共振周波数というのは100Hz前後のものが多かったりしますから、世の中のスピーカーというもので音楽の低音を楽しもうと思ったら、一ひねりもふたひねりもしてある製品でなければムリ、という仕組みになっていたりします。
スピーカーユニットを密閉式の箱に入れてスピーカーシステムを作り、周波数特性を取ると、なだらかに低音にいくに従って音が小さくなる特性になるものが多く、それを改善するための一つがバスレフシステムというものです。これは、箱に低音の共振を持たせたものです。ギターの胴も共鳴箱ですけども、ギターの箱の共鳴は割と幅広い周波数で共鳴するように作られているのに対し、バスレフスピーカーは特定の音にだけ共鳴するように作られます。スピーカーユニットの最低共振周波数とその箱とのかんけいで、なだらかに低音が出にくくなる密閉箱よりも、フラットな特性の低音が出せるようになるのですけど、あるところでストンと落ちる特性になります。バスレフの共鳴周波数をもっと下げると、もっと低いところまで低音が出せるようにチューニング出来まが、広がる手前の(上の)周波数のところに、くぼみが出来ます(鳴りにくいところが出来る)。くぼみが出来ても、低いところまで鳴るようになって迫力が得られたら成功だし、かえってそれで低音の量感が不足してしまうこともあり得て、これは実際にテストしてほどよいところを探る、なんてことが行われたりします。
これを高度に複雑に行ったものがBOSEのアコースティックなんとかシステムというもので、びっくりするほど迫力ある低音が出るのだけど、ふくよかななりの低音楽器のニュアンスは出せなかったりすると言う、まぁ、そんなものもあります。
これはムービングコイル方式のスピーカーを使う以上はずっとこんな調子なんだろうと思います。
エジソンからちょっとあとずっと続いているわけです。
ブラウン管はようやく最近製造中止になりました。
次はムービングコイル式のスピーカーの代わりになる何かが発明される番だと思います。スタックスの静電式というものが古くからありますけどドライブユニットが特殊で高価なせいか全く普及してる様子はないようです。
で、話が脱線しましたけど、ATH-WS70も、バスレフ式のスピーカーユニットの話と同じような感じの低音であることは感じていたので、「低音が不足している」と書いた人がいると言うことは、これに関係しているのかもしれないと思いました。
そして、ソース(聞いたCD)はなんなのか気になるところです。
ATH-WS70はソリッドベースシステムというユニットの後ろ側に共鳴空間があって低音が強調されているという話なので、聞こえにくい(窪んだ帯域)周波数が出来てしまっているのかもしれません。そこの部分の音が入っているCDを普段聞いている人がこのヘッドフォンを使ってしまったのかもしれないと思うと、あり得る話です。
で、ATH-WS70を使って、「荒井由実」の「ひこうき雲」を聞いていたときに、バスドラが聞こえにくいということを発見。このアルバムは元々バスドラは小さな音で聞こえます。このアルバムに限らず、低音域がタイトな音で収録されているCDを十分な低音間で再生できる装置というのはあまりない気がします。ビリージョエルの最初の方のものも低音の録音技術は優れている(低い音までしっかり録られている)けども、響きがタイトなので装置を選ぶ気がします。ひこうき雲を収録したのはスタジオアルファで、ここの録音もアナログ時代にしてはタイトなドラムだったようで、この辺の事情があるのか(聞く装置しだいでしっかり響く低音なのかもしれん)、とにかくひこうき雲のバスドラは、私には小さく聞こえています。(アルファスタジオは埋め込みのツインウーファーがモニターで、ドラムのブースは石畳になっていたとかで、録られた音を聞いていて個性的に感じるけどもそれは録音エンジニアにもそれなりの何かポリシーがあるんだと思う。これはこれで調べてみるとおもしろいかもしれないけどはまり込みそうだからしない笑)
そのひこうき雲のバスドラがATH-WS70で聞こえない場面がほとんどになってしまっています。
試しにビクターのNC80につなぎ替えて聞いてみると、なんと、聞こえるではあーりませんか。
うーむ。
これはどうしたもんか。
チューニングをが変わった次モデルが出るのか期待することにしようっと。
バスレフのチューニングのような共鳴系の音というのは、共振Qというものがとても高いので、1/3オクターブバンドのグライコみたいなものでは、上の窪んだ帯域を持ち上げるなんてことはちょっとムリです。Qを可変することが可能なパラメトリックイコライザーでも、かなり極端な設定にしないといけないはずだし、悪影響もあると思います。特定のCDを聞くために割り切ってそれをやってみることもおもしろいかもしれませんが、数十万しそうな機械を7000円で購入できる装着感のきついATH-WS70でやるのも現実味がないですよね。
まあしかし、聞こえるものが聞こえない今回のパターンは特別な例だとおもわれます。
ATH-WS70の迫力低音はこれはこれでおもしろいし、今のところ私には空間構成力と名付けられるかもしれないこのヘッドフォンの能力は、いろんな音楽を楽しく聴かせてくれる存在ではあります。弦楽器がリアルだしなんといってもピアノが軽やかに鳴って鳴ってくれるのが嬉しいです。
クラッシックも楽しいです。低音強調がちょっと大げさで、クラッシックの場合コントラバスがこんなに鳴り響いているホールなんてあり得んと思いつつも、脳内補正しつつ聞いてしまうと言うわけです。(ATH-WS70のひこうき雲ではフロアタムの音があり得なく大きく聞こえますけど、MP-NC80ではバランスの取れた音量で聞こえます。ATH-WS70はバスドラが消えて、フロアタムがでかく聞こえる)
Posted by ひで at
19:51
│Comments(0)
2010年05月24日
音の良いヘッドフォンがほしい
最近、iPhoneで音楽を聞くのにはまっています。
もともと音楽を聴くのは好きだったのだけど、ちゃんとした再生装置を持たないまま長いこと経ってしまいました。もっぱらAMラジオの流し聞きが主。そして数年前にSDオーディオの7000円くらいのプレーヤとFMトランスミッタを買って、FMラジカセで音楽を聴いたり。それも1年くらいしたらあまりやらなくなりました。
その一方で、世間ではiPodが流行していたわけですけど、それを買うお小遣いがないのでずっと見送っておりました。
そして、年末、iPhoneの実質0円キャンペーンが始まっていまして、元もともっていたボーダフォンを機種変更してはれてiPhoneを持ったというわけです。
しばらくはそれでネットの掲示板を見たり、GPSとグーぐるマップに驚いたり、iTuneにCDをインポートして音楽を入れてみたりしていて、たまには付属のイヤフォンで聞いてみたりしていたわけです。
その音楽ですが、元来イヤフォンとかヘッドフォンは好きではなかったんです。それは、頭の中で音が鳴る感じがイヤだからです。なので、数年前に購入したFMトランスミッタをiPhoneにつなぎ、ラジカセで音楽を聴いていました。
聞いていると、なんだか音がいい感じがします。もともとオーディオの世界には関心があるのですが、ネットでiPodやiPhoneの評判を見る限り、「しょせんは携帯プレーヤ」ということで、音が悪いものだといわれています。そして、携帯プレーヤの中でもソニーなんかと比べると全然悪い、ということです。なのでそう私も思っていたのですけど、実際に聞くと、なかなか良いものかもしれないと思えてきました。
FMラジカセでも、高音の切れなどがなかなかよさそうな感じがする。なるほど、世界的に売れるからにはそれなりにものがいいんだなという気がしてきました。
そして、付属のイヤフォンで聞くと、音の傾向は昔のコンポーネントステレオでいうところのパイオニアなどのレコードプレーヤに標準でついてきたPC100とかのカートリッジみたいに、レンジは広くなくて音の表情は乏しいものの、バランスがよくまとまっていて可もないけれどこれといって悪いところがない、みたいな音の質です。
それよりなにより、聞くうちにわかってきたのだけど、イヤフォンで聴く音楽というのがそれなりに面白いんですね。なんというか、音楽を虫眼鏡で見るような、細部の音がはっきり聞こえて実に面白い。頭の中で鳴り響く不自然さはあるものの、これが面白くなってきた。
そうすると、もう少し音のいいもので聴きたくなってくる。
iPhoneそのものはいい音を持っていそうで、FMラジカセで感じる音の切れからすれば、付属のイヤフォンが質を落としているのかもしれないと思い始めました。
で、無駄遣いは出来ないものの、どうしても確認したくなって、パソコンショップで2300円ほどの値段で売っていたオーディオテクニカのイヤフォンを購入してみました。何はともあれ比較の対象を手に入れたかったわけです。聞いてみた結果、高音域が強くて中低音が聞こえにくくなりました。高音域も独特のカラーがついています。軽い響きの高音で、これはこれでイヤな感じではなく、好きな人には好きになれる感じの音のような気がします。
そうこうしていたら、iPhoneを紛失してしまいました。
かなりのショック。ソフトバンクのショップで聞いてみると、保険というものはないのだそうで、定価で買い直しになるということでした。32Gなので7万7千円です。この値段のプレーヤーだからそこそこ音がよくても不思議ではない気がします。
とても買えないので、その間、ドコモの携帯で音楽を聴くことにしました。
イヤフォンは先程のATの2300円のもので、本体はグーぐるフォンというAH-03Aというものです。これにMP3の音楽ファイルを転送し、聞いたりしていたのですが、低音から高音までiPhoneと同じように聞けるものの、音の表情が死んでしまっています。
音というものは不思議で、再生音域の広さだけではないんですね。なんとも音に精彩がない。表情がない。
聞けば聞くほどその感じが強く感じられてきて、iPhoneで聞いていたときのような楽しさがないのです。
聞いていると、音楽を聴くことが嫌いになってきそうなくらい表情がない音なので、せっかく生活に音楽が入ってきそうになってたところ、また聞かなくなってはつまらなくなってしまうので、聞くのをやめてしまいました。
そして、ヒョンなところからiPhoneは見つかりました。さっそく付属イヤフォンで聞いてみたのはいうまでもありません。
この付属イヤフォン、単品で買うと4800円ほどするんですね。輸入物だから高いのか、値段の通りに「付属」レベルではなくてちゃんと4800円の価値を持っているものなのか、なかなか判断に迷います。
装着しても回りの音は聞こえるし、音の分解能は良いと思うし、わりと低い音までちゃんと聞こえる実力派です。これも世界で売れるだけのことはあると思えます。
さて、もう少しいい音で楽しめるはずだと思うので、インターネットで情報を仕入れてみることにしたのですが、これがまるでわからないのです。
インターネットで情報化というけれど、検索して出てくるのはブログの感想みたいなもの。しかもその量たるや大量すぎてとても読みきれない。
どんな人がどんな基準で書いてるのかも不明な文章がワンサと出てきて、結局何がいいのかわからずじまい。
わかったのは、ソニーのヌーダとかいうものの900という品番のものがとても評判を受けて売れたのだとか。これは一万円くらい。
パソコンショップでそれの後継と思われるものが12000円ほどで売っていましたが、買うのは躊躇しました。
というのは、音響製品、家電製品、電気製品で音に関わるものは質の良し悪しの差が激しすぎるのをよく知っているからです。
後継機種、姉妹品といっても、びっくりするくらい音に違いがあるのはざらだからです。
評判を鵜呑みにすることは危ないけれど、かといって冒険しなければ新しい世界は体験できない。思い切ってヘッドフォンを購入してみました。
選んだのはそのショップに売っていた5800円のヘッドフォン。
これはビクターのHP-NC80というものです。
ノイズキャンセリング機能付。
この機能はすばらしく、車の中で聞くことの多い私にはぴったりのものでした。
車のエンジンノイズというのは音のスペクトルが広くて、ものすごく低い音から高い音までが連続ででていて、特に社内の走行時のノイズというのは低音域の洪水なので、走行中音楽を聴くと低音域がすっぽり聞こえなくなってしまいます。
この低音域のノイズをかなり抑えてくれるのです。
加えて、このヘッドフォンはものすごく低音域が強く出てくる。イヤフォンを聞き慣れてしまうと、下手すると音がこもっているのかと思えるくらいに低音域が膨らんで聞こえます。
その代わり、高音域が小さくなってしまった感じがするのですが、不思議なことに聞こえているはずの音はちゃんと聞こえていて、線の細い表現ながらしっかり高音域まで聞こえるのでかなり満足できました。
二月ほど使ったのですが、やっぱり暗めの表現の音であることは間違いのないところなので、別なものが聞いてみたいと思い始めました。
そこで、清水の舞台から飛び下りるつもりで別なものを購入してみることに。
今度は12000円くらいの予算で考えつつショップに行ってみると、あのドイツの音響メーカー、ゼンハイザーの小型ヘッドフォンが7000円でありました。ヘッドフォンといっても、耳掛け型にヘッドバンドがついているような小さなもの。PX200というもの。これはネットのビッグカメラおすすめの商品で見かけたこともあります。予定より安いしゼンハイザーだしということで買ってみることにしました。製造は中国です。
聞いてみたところ、一瞬にして違和感が。
まるで、大型スピーカーシステムのスコーカーの音だけを聞いているような、中音域だけの音です。
昔の録音の曲の、出だしのところでマスターテープのヒスノイズが聞こえたりしたのでかなり分解能は高そうだけれども、なんとも中音域だけの音。
それでもせっかく買ったのだからと聞いていました。
中音域だけとはいえ、共鳴や特性にピークがあるから強調されているのではなさそうで、長く聞いていても疲れない音ではあります。ビクターのヘッドフォンが暗くてボーカルが沈む傾向なのと正反対でボーカルだけは元気よくはっきり前面に出て聞こえて
きます。イヤフォンを耳に押しつけると、低音域もちゃんと出ているのが確認できます。
このヘッドフォン、パッケージにBASSという文字のシールが貼ってあって、いかにもイヤフォンで低音が物足りなく思っている人に勧めているかのような印象だったのですが、そのbassが全く聞こえないのですからなにおかいわんやなのです。
これも我慢して聞いていると音楽が嫌いになりそうだから、聞くのをやめることにしました。
手元に持っていても残念な思いがいつまでも残りそうなので、普段話し相手をしてくれる高校生くんにあげることにしました。あげるなら新しいうちにということで、次の日に実行。
いいものに当たるまでこんな買い物を続けなければいけないのかと思いつつ、知人と話をしていると、ベスト電器のしんえい店で、ヘッドフォンの視聴が出来たよという耳寄り情報が。
で、早速いってきました。仕事帰りで閉店が近かったのだけれども。
同じソースがヘッドフォンもイヤフォンもそれぞれ30種類くらい視聴できるようになっているではありませんか。
一つのシマの片側がヘッドフォンで、反対側がイヤフォンでした。
そのシマの角(パチンコでいえば、一番出る場所?)のところはATの一押し新製品?のディスプレーがあって、飾りの石やワインボトルとともに新型ヘッドフォンが飾ってあります。
それならばとさっそく掛けてみると、なるほど、高級オーディオの世界みたいな音が広がりました。モダンジャズのカルテットみたいなソースが流れています。
時間がないので、次々に試聴していきます。
イヤフォン(カナル型)は総じて低音域のないいわゆるイヤフォンの音であるということがわかりました。
中~中高音が強く聞こえるものがほぼ全部。
その中でも、フラットで広いレンジが聞こえて音楽向きかなと思えるのは、ソニーの300EXとかいうものと、ATの70という数字の入ったものの二つでした。どちらも数千円で、それより高いものはいくつもありましたけど、よさそうなものはそのふたつ。
ヘッドフォンがやはりいい音がするのでヘッドフォン一択です。
4800円くらいから4万くらいのものまでありましたが、音楽鑑賞向き? で、買ってみたいものは4つ程でした。
一つは最初に聞いたATのATH-WS70というもので、ケースがアルミダイキャスト削りだしとかいうもの。9980円。次はATの25000円のものとソニーの30000円のもの。後もう一つは、同じく3万円ほどのもの。
時間が10分くらいしかなかったので、型番や正確な金額は覚えられませんでしたけど、パッと聞いてバランスの良いものはこの4つでした。
なかでも、最初に聞いたATの9980円のものは、異次元の低音です。
これだけは飛び抜けていました。
他の2.5万、3万のものはそこまでの低音ではないものの、上質で明るく繊細で温かみのある音楽を楽しめそうなバランスのいい音がしていました。
その4つを何度か比較。
それ以外の高いモデルは、高音域でハイハットやシンバルが一本調子になったり独自のカラーリングになったり、そもそもの音のバランスに問題がありそうだったりでした。4万のものは何かの間違いでは? というほど、レンジの狭い精気のない音がしていたのには驚きました。
最終的にはATの2.5万とソニーの3万。それぞれ定価は31500円と38150円、みたいな値段だったと思います。それがいい音でした。あとはATの9980円。
この3つのうち音のバランスは最初の二つがいいのだけど、ATの9980円の低域だけはとにかく別次元です。
低音が強調されているということではなくて、かなり本気の低音が再生されるんです。
そして分解能が高い。
ピアノの音がディレイ処理されているのか、最初の二つで聞くと、一台のピアノに聞こえるものが、9980円では二つに聞こえる。あと、演奏中と、演奏が終わったときとで、空間が鳴ってる感じが消えたり始まったりというそのような雰囲気も伝える。これはガチで異次元の音です。しかし、高音域の音の表現がうすーい感じになってしまっていて、最初の二つのモデルにある温かく包むような表現がない。この中高音で、低音域が9980円のものだと完璧なような気がするけど、しかし、空気感や分解能のよさはちょっと9980円独自のものがあります。
打楽器と弦楽器の表現が良くて、バスドラがちゃんと太鼓の音になってるし、弦楽器も弾き手の演奏の様子が伝わるようなリアリティーがある。弓で弾くコントラバスなんかは、演奏の様子が見えてくるような気もするくらいなので、高音域が薄い表現に思えるけれど、これはこれでこのバランスを支えているのかもしれないと思いました。
なので、相当迷ったのだけど、考えてみれば価格差が3倍ではないですか。
コストパフォーマンス的には9980円が相当いいことになります。
音楽を聞く場合に大事なポイントは、音のファンダメンタル領域をしっかり出せる装置が優れているということがありますので、低音再生が異次元にいいこのモデルを選ぶことにします。
なので、今回はATの9980円を購入することにしました。
ビクターの5800円も低音が楽しめてなかなか良かったのだけど、分解能がATの9980円に劣ります。
ちなみに、ATH-WS50という兄弟モデルが6680円で並んでいましたが、全く別の音(音色的には同じ傾向だけど、音域がナローで音がダマになっている)でした。
「音がダマになっている」というのは、こういうことです。再生している音楽の音が、「音楽の音」というひとかたまりの音になっているということです。
いまATの9980円のモデルを聞いているのですが、いままで使っていたビクターのものがいわゆる聞こえている音を全部ひっくるめて「ヘッドフォンの音」という感じなのに対し、ATH-WS70で聞くと、「バイオリンならバイオリン、それも第一第二、ホルンやフルート、それぞれの楽器がそれぞれの音で、しかも演奏者それぞれの演奏の様子が全部区別できるほど別々に聞こえ、その別々の楽器の音が全体としてアンサンブルになっていてハーモニーを奏でている感じ」が、楽しめるのです。
最初のうちはJポップで打楽器弦楽器の音がいいなぁというくらいに思っていたのですけども、クラッシックの、オーケストラものなどを聞いてみてこのことがわかってびっくりした次第です。
とにかくクラッシックを聞くのが楽しい。
クラッシックがこんな音楽だったのかと、聞いたことがない人もびっくりできるのではと、思えます。
ただ、高音域の表現が薄くて、ハイハットなどの音がどっかにいってしまう感じなのは大変惜しいのですけど、ここが明るいキャラクターになれば、たぶんメーカーも5万くらいで売りたい音になるのでしょうか。
低音楽器や打楽器弦楽器のアタックの強い楽器の音はちょっと他にない感じがします。強めに出ているバランスなのは、ヘッドフォンアンプ(8バンド以上のグライコか出来れば4エレメント以上のパラメトリックイコライザーが付いている)で補正すれば問題ないと思われますけど、車の中で聞くことの多い私には、むしろこのくらいが楽しいです。
CP的にはものすごく高いです。
ホント、音楽を聴くのが楽しみになります。
ネットで情報を見ていると、iPodクラスの低レベルな再生装置にはこの程度で十分でしょう、みたいなことがよく書いてありますけど、なかなかどうして、かなりいい音で楽しめることがわかりました。
iPodは確かに、すこし粗削りでスムーズさがないのかもしれませんけど、元気で明るい個性としてそれも楽しめるので、やっぱり世界で売れるだけの製品ではあると思います。
今度はもっといろんな製品が試聴できるお店があれば、出かけていって聞いてみたいと思います。
(急いで書いたのでひどい文章ですけど、読んでいただいた方には感謝いたします)
もともと音楽を聴くのは好きだったのだけど、ちゃんとした再生装置を持たないまま長いこと経ってしまいました。もっぱらAMラジオの流し聞きが主。そして数年前にSDオーディオの7000円くらいのプレーヤとFMトランスミッタを買って、FMラジカセで音楽を聴いたり。それも1年くらいしたらあまりやらなくなりました。
その一方で、世間ではiPodが流行していたわけですけど、それを買うお小遣いがないのでずっと見送っておりました。
そして、年末、iPhoneの実質0円キャンペーンが始まっていまして、元もともっていたボーダフォンを機種変更してはれてiPhoneを持ったというわけです。
しばらくはそれでネットの掲示板を見たり、GPSとグーぐるマップに驚いたり、iTuneにCDをインポートして音楽を入れてみたりしていて、たまには付属のイヤフォンで聞いてみたりしていたわけです。
その音楽ですが、元来イヤフォンとかヘッドフォンは好きではなかったんです。それは、頭の中で音が鳴る感じがイヤだからです。なので、数年前に購入したFMトランスミッタをiPhoneにつなぎ、ラジカセで音楽を聴いていました。
聞いていると、なんだか音がいい感じがします。もともとオーディオの世界には関心があるのですが、ネットでiPodやiPhoneの評判を見る限り、「しょせんは携帯プレーヤ」ということで、音が悪いものだといわれています。そして、携帯プレーヤの中でもソニーなんかと比べると全然悪い、ということです。なのでそう私も思っていたのですけど、実際に聞くと、なかなか良いものかもしれないと思えてきました。
FMラジカセでも、高音の切れなどがなかなかよさそうな感じがする。なるほど、世界的に売れるからにはそれなりにものがいいんだなという気がしてきました。
そして、付属のイヤフォンで聞くと、音の傾向は昔のコンポーネントステレオでいうところのパイオニアなどのレコードプレーヤに標準でついてきたPC100とかのカートリッジみたいに、レンジは広くなくて音の表情は乏しいものの、バランスがよくまとまっていて可もないけれどこれといって悪いところがない、みたいな音の質です。
それよりなにより、聞くうちにわかってきたのだけど、イヤフォンで聴く音楽というのがそれなりに面白いんですね。なんというか、音楽を虫眼鏡で見るような、細部の音がはっきり聞こえて実に面白い。頭の中で鳴り響く不自然さはあるものの、これが面白くなってきた。
そうすると、もう少し音のいいもので聴きたくなってくる。
iPhoneそのものはいい音を持っていそうで、FMラジカセで感じる音の切れからすれば、付属のイヤフォンが質を落としているのかもしれないと思い始めました。
で、無駄遣いは出来ないものの、どうしても確認したくなって、パソコンショップで2300円ほどの値段で売っていたオーディオテクニカのイヤフォンを購入してみました。何はともあれ比較の対象を手に入れたかったわけです。聞いてみた結果、高音域が強くて中低音が聞こえにくくなりました。高音域も独特のカラーがついています。軽い響きの高音で、これはこれでイヤな感じではなく、好きな人には好きになれる感じの音のような気がします。
そうこうしていたら、iPhoneを紛失してしまいました。
かなりのショック。ソフトバンクのショップで聞いてみると、保険というものはないのだそうで、定価で買い直しになるということでした。32Gなので7万7千円です。この値段のプレーヤーだからそこそこ音がよくても不思議ではない気がします。
とても買えないので、その間、ドコモの携帯で音楽を聴くことにしました。
イヤフォンは先程のATの2300円のもので、本体はグーぐるフォンというAH-03Aというものです。これにMP3の音楽ファイルを転送し、聞いたりしていたのですが、低音から高音までiPhoneと同じように聞けるものの、音の表情が死んでしまっています。
音というものは不思議で、再生音域の広さだけではないんですね。なんとも音に精彩がない。表情がない。
聞けば聞くほどその感じが強く感じられてきて、iPhoneで聞いていたときのような楽しさがないのです。
聞いていると、音楽を聴くことが嫌いになってきそうなくらい表情がない音なので、せっかく生活に音楽が入ってきそうになってたところ、また聞かなくなってはつまらなくなってしまうので、聞くのをやめてしまいました。
そして、ヒョンなところからiPhoneは見つかりました。さっそく付属イヤフォンで聞いてみたのはいうまでもありません。
この付属イヤフォン、単品で買うと4800円ほどするんですね。輸入物だから高いのか、値段の通りに「付属」レベルではなくてちゃんと4800円の価値を持っているものなのか、なかなか判断に迷います。
装着しても回りの音は聞こえるし、音の分解能は良いと思うし、わりと低い音までちゃんと聞こえる実力派です。これも世界で売れるだけのことはあると思えます。
さて、もう少しいい音で楽しめるはずだと思うので、インターネットで情報を仕入れてみることにしたのですが、これがまるでわからないのです。
インターネットで情報化というけれど、検索して出てくるのはブログの感想みたいなもの。しかもその量たるや大量すぎてとても読みきれない。
どんな人がどんな基準で書いてるのかも不明な文章がワンサと出てきて、結局何がいいのかわからずじまい。
わかったのは、ソニーのヌーダとかいうものの900という品番のものがとても評判を受けて売れたのだとか。これは一万円くらい。
パソコンショップでそれの後継と思われるものが12000円ほどで売っていましたが、買うのは躊躇しました。
というのは、音響製品、家電製品、電気製品で音に関わるものは質の良し悪しの差が激しすぎるのをよく知っているからです。
後継機種、姉妹品といっても、びっくりするくらい音に違いがあるのはざらだからです。
評判を鵜呑みにすることは危ないけれど、かといって冒険しなければ新しい世界は体験できない。思い切ってヘッドフォンを購入してみました。
選んだのはそのショップに売っていた5800円のヘッドフォン。
これはビクターのHP-NC80というものです。
ノイズキャンセリング機能付。
この機能はすばらしく、車の中で聞くことの多い私にはぴったりのものでした。
車のエンジンノイズというのは音のスペクトルが広くて、ものすごく低い音から高い音までが連続ででていて、特に社内の走行時のノイズというのは低音域の洪水なので、走行中音楽を聴くと低音域がすっぽり聞こえなくなってしまいます。
この低音域のノイズをかなり抑えてくれるのです。
加えて、このヘッドフォンはものすごく低音域が強く出てくる。イヤフォンを聞き慣れてしまうと、下手すると音がこもっているのかと思えるくらいに低音域が膨らんで聞こえます。
その代わり、高音域が小さくなってしまった感じがするのですが、不思議なことに聞こえているはずの音はちゃんと聞こえていて、線の細い表現ながらしっかり高音域まで聞こえるのでかなり満足できました。
二月ほど使ったのですが、やっぱり暗めの表現の音であることは間違いのないところなので、別なものが聞いてみたいと思い始めました。
そこで、清水の舞台から飛び下りるつもりで別なものを購入してみることに。
今度は12000円くらいの予算で考えつつショップに行ってみると、あのドイツの音響メーカー、ゼンハイザーの小型ヘッドフォンが7000円でありました。ヘッドフォンといっても、耳掛け型にヘッドバンドがついているような小さなもの。PX200というもの。これはネットのビッグカメラおすすめの商品で見かけたこともあります。予定より安いしゼンハイザーだしということで買ってみることにしました。製造は中国です。
聞いてみたところ、一瞬にして違和感が。
まるで、大型スピーカーシステムのスコーカーの音だけを聞いているような、中音域だけの音です。
昔の録音の曲の、出だしのところでマスターテープのヒスノイズが聞こえたりしたのでかなり分解能は高そうだけれども、なんとも中音域だけの音。
それでもせっかく買ったのだからと聞いていました。
中音域だけとはいえ、共鳴や特性にピークがあるから強調されているのではなさそうで、長く聞いていても疲れない音ではあります。ビクターのヘッドフォンが暗くてボーカルが沈む傾向なのと正反対でボーカルだけは元気よくはっきり前面に出て聞こえて
きます。イヤフォンを耳に押しつけると、低音域もちゃんと出ているのが確認できます。
このヘッドフォン、パッケージにBASSという文字のシールが貼ってあって、いかにもイヤフォンで低音が物足りなく思っている人に勧めているかのような印象だったのですが、そのbassが全く聞こえないのですからなにおかいわんやなのです。
これも我慢して聞いていると音楽が嫌いになりそうだから、聞くのをやめることにしました。
手元に持っていても残念な思いがいつまでも残りそうなので、普段話し相手をしてくれる高校生くんにあげることにしました。あげるなら新しいうちにということで、次の日に実行。
いいものに当たるまでこんな買い物を続けなければいけないのかと思いつつ、知人と話をしていると、ベスト電器のしんえい店で、ヘッドフォンの視聴が出来たよという耳寄り情報が。
で、早速いってきました。仕事帰りで閉店が近かったのだけれども。
同じソースがヘッドフォンもイヤフォンもそれぞれ30種類くらい視聴できるようになっているではありませんか。
一つのシマの片側がヘッドフォンで、反対側がイヤフォンでした。
そのシマの角(パチンコでいえば、一番出る場所?)のところはATの一押し新製品?のディスプレーがあって、飾りの石やワインボトルとともに新型ヘッドフォンが飾ってあります。
それならばとさっそく掛けてみると、なるほど、高級オーディオの世界みたいな音が広がりました。モダンジャズのカルテットみたいなソースが流れています。
時間がないので、次々に試聴していきます。
イヤフォン(カナル型)は総じて低音域のないいわゆるイヤフォンの音であるということがわかりました。
中~中高音が強く聞こえるものがほぼ全部。
その中でも、フラットで広いレンジが聞こえて音楽向きかなと思えるのは、ソニーの300EXとかいうものと、ATの70という数字の入ったものの二つでした。どちらも数千円で、それより高いものはいくつもありましたけど、よさそうなものはそのふたつ。
ヘッドフォンがやはりいい音がするのでヘッドフォン一択です。
4800円くらいから4万くらいのものまでありましたが、音楽鑑賞向き? で、買ってみたいものは4つ程でした。
一つは最初に聞いたATのATH-WS70というもので、ケースがアルミダイキャスト削りだしとかいうもの。9980円。次はATの25000円のものとソニーの30000円のもの。後もう一つは、同じく3万円ほどのもの。
時間が10分くらいしかなかったので、型番や正確な金額は覚えられませんでしたけど、パッと聞いてバランスの良いものはこの4つでした。
なかでも、最初に聞いたATの9980円のものは、異次元の低音です。
これだけは飛び抜けていました。
他の2.5万、3万のものはそこまでの低音ではないものの、上質で明るく繊細で温かみのある音楽を楽しめそうなバランスのいい音がしていました。
その4つを何度か比較。
それ以外の高いモデルは、高音域でハイハットやシンバルが一本調子になったり独自のカラーリングになったり、そもそもの音のバランスに問題がありそうだったりでした。4万のものは何かの間違いでは? というほど、レンジの狭い精気のない音がしていたのには驚きました。
最終的にはATの2.5万とソニーの3万。それぞれ定価は31500円と38150円、みたいな値段だったと思います。それがいい音でした。あとはATの9980円。
この3つのうち音のバランスは最初の二つがいいのだけど、ATの9980円の低域だけはとにかく別次元です。
低音が強調されているということではなくて、かなり本気の低音が再生されるんです。
そして分解能が高い。
ピアノの音がディレイ処理されているのか、最初の二つで聞くと、一台のピアノに聞こえるものが、9980円では二つに聞こえる。あと、演奏中と、演奏が終わったときとで、空間が鳴ってる感じが消えたり始まったりというそのような雰囲気も伝える。これはガチで異次元の音です。しかし、高音域の音の表現がうすーい感じになってしまっていて、最初の二つのモデルにある温かく包むような表現がない。この中高音で、低音域が9980円のものだと完璧なような気がするけど、しかし、空気感や分解能のよさはちょっと9980円独自のものがあります。
打楽器と弦楽器の表現が良くて、バスドラがちゃんと太鼓の音になってるし、弦楽器も弾き手の演奏の様子が伝わるようなリアリティーがある。弓で弾くコントラバスなんかは、演奏の様子が見えてくるような気もするくらいなので、高音域が薄い表現に思えるけれど、これはこれでこのバランスを支えているのかもしれないと思いました。
なので、相当迷ったのだけど、考えてみれば価格差が3倍ではないですか。
コストパフォーマンス的には9980円が相当いいことになります。
音楽を聞く場合に大事なポイントは、音のファンダメンタル領域をしっかり出せる装置が優れているということがありますので、低音再生が異次元にいいこのモデルを選ぶことにします。
なので、今回はATの9980円を購入することにしました。
ビクターの5800円も低音が楽しめてなかなか良かったのだけど、分解能がATの9980円に劣ります。
ちなみに、ATH-WS50という兄弟モデルが6680円で並んでいましたが、全く別の音(音色的には同じ傾向だけど、音域がナローで音がダマになっている)でした。
「音がダマになっている」というのは、こういうことです。再生している音楽の音が、「音楽の音」というひとかたまりの音になっているということです。
いまATの9980円のモデルを聞いているのですが、いままで使っていたビクターのものがいわゆる聞こえている音を全部ひっくるめて「ヘッドフォンの音」という感じなのに対し、ATH-WS70で聞くと、「バイオリンならバイオリン、それも第一第二、ホルンやフルート、それぞれの楽器がそれぞれの音で、しかも演奏者それぞれの演奏の様子が全部区別できるほど別々に聞こえ、その別々の楽器の音が全体としてアンサンブルになっていてハーモニーを奏でている感じ」が、楽しめるのです。
最初のうちはJポップで打楽器弦楽器の音がいいなぁというくらいに思っていたのですけども、クラッシックの、オーケストラものなどを聞いてみてこのことがわかってびっくりした次第です。
とにかくクラッシックを聞くのが楽しい。
クラッシックがこんな音楽だったのかと、聞いたことがない人もびっくりできるのではと、思えます。
ただ、高音域の表現が薄くて、ハイハットなどの音がどっかにいってしまう感じなのは大変惜しいのですけど、ここが明るいキャラクターになれば、たぶんメーカーも5万くらいで売りたい音になるのでしょうか。
低音楽器や打楽器弦楽器のアタックの強い楽器の音はちょっと他にない感じがします。強めに出ているバランスなのは、ヘッドフォンアンプ(8バンド以上のグライコか出来れば4エレメント以上のパラメトリックイコライザーが付いている)で補正すれば問題ないと思われますけど、車の中で聞くことの多い私には、むしろこのくらいが楽しいです。
CP的にはものすごく高いです。
ホント、音楽を聴くのが楽しみになります。
ネットで情報を見ていると、iPodクラスの低レベルな再生装置にはこの程度で十分でしょう、みたいなことがよく書いてありますけど、なかなかどうして、かなりいい音で楽しめることがわかりました。
iPodは確かに、すこし粗削りでスムーズさがないのかもしれませんけど、元気で明るい個性としてそれも楽しめるので、やっぱり世界で売れるだけの製品ではあると思います。
今度はもっといろんな製品が試聴できるお店があれば、出かけていって聞いてみたいと思います。
(急いで書いたのでひどい文章ですけど、読んでいただいた方には感謝いたします)
Posted by ひで at
01:51
│Comments(3)
2010年05月10日
kyuリーグ2010第5節、ヴォルカvs川添クラブ(佐賀)
すんごくひっさしぶりにヴォルカ鹿児島の試合を見に行きました。
結果はご存じのように3-0でヴォルカ鹿児島の快勝。
まぁ、私は相変わらず運動音痴でサッカーが目の前で行われていて、それをまじかで見ていたとしてもなんにも見えていないというのが悲しいところではありますけども、他のサイトでチェックしたところによると今日の試合はとてもいい試合だったようです。
写真を貼りますね。

これは辻選手のシュート直後の画像。
今日は積極的にFWの選手がゴール前でシュートを打つ場面がたくさんありました。
たくさんあったのですけど、外してしまうことも多かったんです。
この場面も、相手からのプレスをはねのけ絶好の位置からシュートを打ったものの上にそれてしまったんです。
それを見届けながら、あーこれじゃいけないんだけどナァ、みたいな表情で、相手に押されながらもそれていったボールを見ていました。惜しい、とかじゃなくて、これじゃいけない、という感じだったのが印象に残っています。
夕方、ラジオでヴォルカの試合が取り上げられまして、辻選手本人のインタビューも流れました。曰く、
今年は上に上がる大事な年として取れるところではどんどん点を取っておかなければならないのに、取れなかったのが悔しいし反省点として意識しているというようなことを言っていました。5点くらいいれてもおかしくなかったのに、ということでした。実際、そのくらいのチャンスを作っていたのだけど、一得点だったのです。
しかし、外したものの、積極的なその姿勢はとても魅力的でした。
次にびっくりしたのは、あの栫選手がヴォルカにいるではあーりませんか。

今年、入ってきたのは噂で聞いていましたし、入って早々、かなりの存在感を出しているし得点に絡む活躍をやっているということは知っていたのですけど、やっぱり生で見ると、噂どおりの存在感。なにかのオーラを出しながらドリブルしている。
この日は観客が入っていて、鴨池であるときもだけど、子供も来ていました。
試合後は出待ちでサインをねだっていました。
人気のバロメーターのようなこのハプニング? は、当日取材に来ていた南日本放送のテレビ・ラジオ、南日本新聞の記者から取材を受けていました。当然のように私も撮りたかったけど、離れた場所だったので取れなかったわけです。それはそうと、先程のラジオ番組でその子供のインタビューの様子が流れました。
「ヴォルカの試合を見てどうだった?」
「すごかった。うまい」
「どこがどんなふうに?」
「パスサッカーでボールを回すところが高い技術でうまくてすごい」「トラップがうまくてすごい」などといっていたし、
「すごいと思った選手はいた?」
「かこいくんがすごかった」(くん、かよ!)
「ドリブルでどんどん仕掛けてはいっていくし、パスを出すところでは出すし、すごい選手だとおもった。自分もあんな選手になりたいし、将来ヴォルカに入りたいと思った」
というようなはなしでした。
小学3、4年生くらいの数人の子供たちでしたけど、将来を見据えたリクルート戦略なのかとおもえるほど完璧なるコメントでした。
それにしても、栫選手は存在感ありました。
彼の先輩のOBと話していたんですけど、4月に入ったらしいけど「かなり太ってしまっていてまともに走れんのかなぁと思っていたけど、(私の話を聞くにつけ)やっぱりいいところにいる(ポジション取りがいい)し、持ってるんだなぁ」ってわけで、ぜひとも体を絞っていい選手になってほしいと、思った今日この頃です。
結果はご存じのように3-0でヴォルカ鹿児島の快勝。
まぁ、私は相変わらず運動音痴でサッカーが目の前で行われていて、それをまじかで見ていたとしてもなんにも見えていないというのが悲しいところではありますけども、他のサイトでチェックしたところによると今日の試合はとてもいい試合だったようです。
写真を貼りますね。

これは辻選手のシュート直後の画像。
今日は積極的にFWの選手がゴール前でシュートを打つ場面がたくさんありました。
たくさんあったのですけど、外してしまうことも多かったんです。
この場面も、相手からのプレスをはねのけ絶好の位置からシュートを打ったものの上にそれてしまったんです。
それを見届けながら、あーこれじゃいけないんだけどナァ、みたいな表情で、相手に押されながらもそれていったボールを見ていました。惜しい、とかじゃなくて、これじゃいけない、という感じだったのが印象に残っています。
夕方、ラジオでヴォルカの試合が取り上げられまして、辻選手本人のインタビューも流れました。曰く、
今年は上に上がる大事な年として取れるところではどんどん点を取っておかなければならないのに、取れなかったのが悔しいし反省点として意識しているというようなことを言っていました。5点くらいいれてもおかしくなかったのに、ということでした。実際、そのくらいのチャンスを作っていたのだけど、一得点だったのです。
しかし、外したものの、積極的なその姿勢はとても魅力的でした。
次にびっくりしたのは、あの栫選手がヴォルカにいるではあーりませんか。

今年、入ってきたのは噂で聞いていましたし、入って早々、かなりの存在感を出しているし得点に絡む活躍をやっているということは知っていたのですけど、やっぱり生で見ると、噂どおりの存在感。なにかのオーラを出しながらドリブルしている。
この日は観客が入っていて、鴨池であるときもだけど、子供も来ていました。
試合後は出待ちでサインをねだっていました。
人気のバロメーターのようなこのハプニング? は、当日取材に来ていた南日本放送のテレビ・ラジオ、南日本新聞の記者から取材を受けていました。当然のように私も撮りたかったけど、離れた場所だったので取れなかったわけです。それはそうと、先程のラジオ番組でその子供のインタビューの様子が流れました。
「ヴォルカの試合を見てどうだった?」
「すごかった。うまい」
「どこがどんなふうに?」
「パスサッカーでボールを回すところが高い技術でうまくてすごい」「トラップがうまくてすごい」などといっていたし、
「すごいと思った選手はいた?」
「かこいくんがすごかった」(くん、かよ!)
「ドリブルでどんどん仕掛けてはいっていくし、パスを出すところでは出すし、すごい選手だとおもった。自分もあんな選手になりたいし、将来ヴォルカに入りたいと思った」
というようなはなしでした。
小学3、4年生くらいの数人の子供たちでしたけど、将来を見据えたリクルート戦略なのかとおもえるほど完璧なるコメントでした。
それにしても、栫選手は存在感ありました。
彼の先輩のOBと話していたんですけど、4月に入ったらしいけど「かなり太ってしまっていてまともに走れんのかなぁと思っていたけど、(私の話を聞くにつけ)やっぱりいいところにいる(ポジション取りがいい)し、持ってるんだなぁ」ってわけで、ぜひとも体を絞っていい選手になってほしいと、思った今日この頃です。
Posted by ひで at
00:09
│Comments(4)
2010年02月22日
サガン鳥栖の練習試合(対鹿屋体育大学、カターレ富山)
鹿児島にはプロスポーツチームが多数キャンプにきています。
サッカーのチームは大方キャンプ期間が終了して引き上げたところも多いのですが、鴨池陸上競技場には今日までがサガン鳥栖がいます。練習試合の相手が鹿屋体育大学だと聞き、ひょっとして赤尾君がいるかもしれないと思って出かけたのだけど、いませんでした。4年ですものね。
いくついでに、某巨大掲示板の中にある国内サッカー板のサガン鳥栖スレにお邪魔し、写真に撮りたい選手を聞いてみたところレスポンスがあり、8番と13番を出来れば顔中心に、というリクエストでした。
専門的なことは一つもわからない私ですので、むしろ、ミーハー路線のリクエストなら守備範囲です(笑)。
まずは9番の豊田 陽平 選手のヘディング。


リクエストのあった8番の衛藤 裕 選手。


リクエストのあった13番日高 拓磨 選手。


お名前がわからないけど、30番の選手。

サッカーのチームは大方キャンプ期間が終了して引き上げたところも多いのですが、鴨池陸上競技場には今日までがサガン鳥栖がいます。練習試合の相手が鹿屋体育大学だと聞き、ひょっとして赤尾君がいるかもしれないと思って出かけたのだけど、いませんでした。4年ですものね。
いくついでに、某巨大掲示板の中にある国内サッカー板のサガン鳥栖スレにお邪魔し、写真に撮りたい選手を聞いてみたところレスポンスがあり、8番と13番を出来れば顔中心に、というリクエストでした。
専門的なことは一つもわからない私ですので、むしろ、ミーハー路線のリクエストなら守備範囲です(笑)。
まずは9番の豊田 陽平 選手のヘディング。


リクエストのあった8番の衛藤 裕 選手。


リクエストのあった13番日高 拓磨 選手。


お名前がわからないけど、30番の選手。

Posted by ひで at
00:03
│Comments(0)
2010年02月03日
面白い灰皿
出先で見つけた面白い灰皿。

使えば使うほど、たばこを吸いたくなくなるような灰皿です。
吸う程に灰皿の中が黒く汚れていくけど、自分の肺の。中も黒くなってるかもとかおもと思うと、気分はブルーに。
不思議な一品です。
どのような発想で企画され、どんな美的センスの人が作ったのか、謎だ。

使えば使うほど、たばこを吸いたくなくなるような灰皿です。
吸う程に灰皿の中が黒く汚れていくけど、自分の肺の。中も黒くなってるかもとかおもと思うと、気分はブルーに。
不思議な一品です。
どのような発想で企画され、どんな美的センスの人が作ったのか、謎だ。
Posted by ひで at
17:42
│Comments(0)